×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
『幻獣ムベンベを追え』は早稲田大学探検部出身の作家、高野秀行による1989年のデビュー作。
コンゴのテレ湖という湖にネッシーのような怪獣が棲んでいるということで、探検部の調査隊一行は現地へ向かう。しかし日本人はほとんど誰も近付かないようなアフリカの小国。
思いっきり、辺境<周縁=マージナル>だ。
そしてすんなりとコンゴまで辿り着かない。ましてや、テレ湖は密林ジャングルの奥地と言えるような場所。高野らは、猿やゴリラや蛇など何でも食して一ヶ月の調査を終えた。
注1)
ムベンベが見つかったか否かは本書を読んでのお楽しみ。ちなみに最近刊行された『コンゴ・ジャーニー』では著者のレドモンド・オハンロンもこのテレ湖へ遠征し、高野が帰国の際にプレゼントした迷彩服を着た「アニャーニャ博士(ドクター)」を書中で改めて見ることができるという。
注2)
早稲田の探検部というと、いまや日本の冒険小説の第一人者である船戸与一や同じく西木正明などを輩出しているが、高野氏はそれに連なる作家。
探検とか冒険というのは、端でクーラーにあたって本で優雅に読んでいると何ともバカバカしいところがある。あえて何でそんなに高い山に登ろうとするのか、どうしてそんな辺境の地まで行って怪獣を探そうとするのか。だが、ある種類の人達というのは、その欲求が抑えられず行動へと移す。それは高野ばかりでないのだ。司馬遼太郎(『街道をゆく』)も梅棹忠夫(『世界言語紀行』)も同様なのである。マージナルなものは人を魅了してやまない。
『フィンランド語は猫の言葉』は翻訳家、稲垣美晴が1970年代にフィンランドへ留学した冒険譚である。芸大生だった稲垣は果敢にヘルシンキ大学へ留学するのだが、その時代であるからなおさら、<冒険譚>といって差し支えないと思う。気候風土が熱帯雨林のジャングルか厳寒の北方かの違いがあるだけで、稲垣は<ムベンベ>ではなく、日本人にとっては幻の言語<フィンランド語>を探索しに行ったのだ。
* * *
最近よく聴くシベリウスをより深く理解するためには、フィンランドの歴史を当然知る必要があろう。また、かのフォン・ノイマンがランド研究所で研究を進めたという「フィンランド音韻論」からして、フィンランド語の音の性質を知ればシベリウスをもっと沢山理解できるに違いない。<タッタタ>という言葉、単語のリズムなのだと、フィンランドのスピーカーメーカーを取材した某オーディオ誌のK編集長は言っていた。シベリウスの音楽もこの音韻に従っているのだという(今回の記事タイトルはフォン・ノイマンからの駄洒落です、、、)。
そこでフィンランド語の入門書を立ち読みしてみたら、
<Hyvää päivää!!>が「こんにちは」とある。
字面からして一筋縄ではいかないことがお分かり頂けよう。おまけにフィンランド語は格変化が15格あって、数字も格変化するという。一体何という言語だ。こういう言葉を理解するのはもはや、真っ暗闇の洞窟探検と同じといえよう。
●関連ブログ
●[23]子音の文化と母音の文化 ~言語からみた音楽性の相違とそれに適したオーディオ再生装置とは~
PR
先週の日曜日に、仕事で神谷町に出かけ、足早に初台のオペラシティーへと向かい、ステーンハンマル友の会が主催するコンサート『北欧音楽の調べ』を聴きに行った。
ステーンハンマルをはじめとして、スウェーデンの作曲家が中国や日本、中東などをモチーフに作曲したものを演奏。選曲に工夫のあるコンサートだった。こちら極東アジアの日本から北欧をイメージするのと同じように、北欧人がオリエンタルを題材にするとどんな曲になるのだろう、という興味を満たすプログラムだった。
会を主宰する和田氏のインタビューが『音楽之友』誌7月号に掲載されている。
W.ペッテション=ベリエル:ノルランド風ラプソディ
H.ルーセンベリ:「14の中国の詩 」より
H.ルーセンベリ:主題と変奏
E.シェーグレン:月光の中の階段
S.フォン・コック:蓮の花
G. ド・フルメリ:「4つの中国の歌」作品66
A.アッテルベリ:組曲 第1番「オリエンタル」(Pカルテット版)
W.ステーンハンマル:ランプのアラジン王子
M.カルコフ:4手の為の「東洋の絵」 作品66d
M.カルコフ:10の日本のロマンス 作品45
W.ペッテション=ベリエル:オリエンタル・ダンス (編曲:和田記代)
ステーンハンマルをはじめとして、スウェーデンの作曲家が中国や日本、中東などをモチーフに作曲したものを演奏。選曲に工夫のあるコンサートだった。こちら極東アジアの日本から北欧をイメージするのと同じように、北欧人がオリエンタルを題材にするとどんな曲になるのだろう、という興味を満たすプログラムだった。
会を主宰する和田氏のインタビューが『音楽之友』誌7月号に掲載されている。
W.ペッテション=ベリエル:ノルランド風ラプソディ
H.ルーセンベリ:「14の中国の詩 」より
H.ルーセンベリ:主題と変奏
E.シェーグレン:月光の中の階段
S.フォン・コック:蓮の花
G. ド・フルメリ:「4つの中国の歌」作品66
A.アッテルベリ:組曲 第1番「オリエンタル」(Pカルテット版)
W.ステーンハンマル:ランプのアラジン王子
M.カルコフ:4手の為の「東洋の絵」 作品66d
M.カルコフ:10の日本のロマンス 作品45
W.ペッテション=ベリエル:オリエンタル・ダンス (編曲:和田記代)
児童作家の<たからしげる>さんがJBLとマランツを晴れて購入し、何でも仕事が手につかない状態なのだという。
今までのBOSE社のものと思しき一体型機よりも飛躍的に音質が向上し、所有のジャズディスクを聴き直したくなって執筆の時間がとれないらしい。
作家に対して何とまあ罪作りなことをしてしまったのだと思いつつ、<いい音になったんだよ>と嬉々として話される様子をみて、こちらの方まで嬉しくなって来たのだった。
首尾よくコンポーネントの結線を終え、機器のセッティングも順調のようで、<在野のオーディオ研究家?>としては実に良かったなあと思っております!
加えて、小学校の夏の緑陰図書(全国学校図書館協議会)に<たから>さんの作品が選ばれたとのことで、小中学生の親御さんへここにお薦め申し上げます。

今までのBOSE社のものと思しき一体型機よりも飛躍的に音質が向上し、所有のジャズディスクを聴き直したくなって執筆の時間がとれないらしい。
作家に対して何とまあ罪作りなことをしてしまったのだと思いつつ、<いい音になったんだよ>と嬉々として話される様子をみて、こちらの方まで嬉しくなって来たのだった。
首尾よくコンポーネントの結線を終え、機器のセッティングも順調のようで、<在野のオーディオ研究家?>としては実に良かったなあと思っております!
加えて、小学校の夏の緑陰図書(全国学校図書館協議会)に<たから>さんの作品が選ばれたとのことで、小中学生の親御さんへここにお薦め申し上げます。
一体何という試合だ!テニスの世界ランク第1位のフェデラーと2位のナダル。フェデラーの全英オープン6連覇の夢を打ち砕いたのは、ナダルであった。
激闘、死闘、両雄一歩も引かず、試合が終わったのは日本時間で午前5時20分。いや、私の寝不足などどうでもよい。
鬼気迫るとはこのことだ。間違いなく歴史の残る名勝負となった。第一セット、第二セットとそれぞれ6-4でナダル。この後、試合はもつれ、何と第三、第四セットはともに7-6でフェデラー。勝負の行方は最終第五セットへ持ち越された。
スポーツというのは世界の1番と2番が本気で戦うと、これほどまでにレベルの高い決闘、果し合いを行うのか。特に最終セットは、一打一打がこの先の生涯を決めることになるかもしれないショットにも関わらず、スーパーショットの連発だった。
ロジャー・フェデラーはテニスの神を味方につけている。0-30とかアドヴァンテージを獲られた時にサービスエースを何度となく繰り出す。それは緊張とか気負いからは解放されている。神が彼にリラックスと自信を授けた。試合の最後のほんの2ポイントのみ見放されただけで、女神はフェデラーに微笑んでいるように見えた。
ラファエル・ナダルはセンターコートの芝の女神よりも、むしろクレー(コート)の風神を守護聖人にしていた訳だから、このウィンブルドンでは自らの力で優勝をもぎ取ったといえる。その筋骨隆々の左腕から、強烈なトップスピンで勝利への執念を乗せてボールを相手コートへ送り込む。勝ちたいという真摯な希求はやがて、神をも蹴散らし、純粋無垢がゆえの芯の強さを∞へと昇華させた。
久々にテニスの醍醐味を味わった。ただいまの時間、午前5時35分。興奮冷めやらない。今日はなかなか寝付けないのではないかと思う。
激闘、死闘、両雄一歩も引かず、試合が終わったのは日本時間で午前5時20分。いや、私の寝不足などどうでもよい。
鬼気迫るとはこのことだ。間違いなく歴史の残る名勝負となった。第一セット、第二セットとそれぞれ6-4でナダル。この後、試合はもつれ、何と第三、第四セットはともに7-6でフェデラー。勝負の行方は最終第五セットへ持ち越された。
スポーツというのは世界の1番と2番が本気で戦うと、これほどまでにレベルの高い決闘、果し合いを行うのか。特に最終セットは、一打一打がこの先の生涯を決めることになるかもしれないショットにも関わらず、スーパーショットの連発だった。
ロジャー・フェデラーはテニスの神を味方につけている。0-30とかアドヴァンテージを獲られた時にサービスエースを何度となく繰り出す。それは緊張とか気負いからは解放されている。神が彼にリラックスと自信を授けた。試合の最後のほんの2ポイントのみ見放されただけで、女神はフェデラーに微笑んでいるように見えた。
ラファエル・ナダルはセンターコートの芝の女神よりも、むしろクレー(コート)の風神を守護聖人にしていた訳だから、このウィンブルドンでは自らの力で優勝をもぎ取ったといえる。その筋骨隆々の左腕から、強烈なトップスピンで勝利への執念を乗せてボールを相手コートへ送り込む。勝ちたいという真摯な希求はやがて、神をも蹴散らし、純粋無垢がゆえの芯の強さを∞へと昇華させた。
久々にテニスの醍醐味を味わった。ただいまの時間、午前5時35分。興奮冷めやらない。今日はなかなか寝付けないのではないかと思う。
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
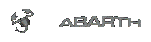
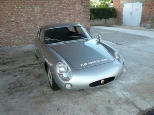
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
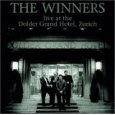
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
