×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
更新にしばし時間を空けてしまいましたが、今回は『晩夏のケーブル討論!』の第3弾をお届けします。まずはbydさんからお寄せ頂いたコメントです。
******************************
私も長年あれこれスピーカーケーブルをとっかえひっかえしてましたが、ベルデンの8460という極細のものに替えてスッキリ低音から高音までよく出ているのでこれにて終了しました。。
******************************
bydさん、有難うございました!
実に含蓄に富んだご意見で、私なりに解釈をさせて頂きますれば、『とっかえひっかえをしなければ意中のケーブルを見つけることはできない』、また『それを経て終了(=終着点)に辿りつく』ことをご指摘されています。
これはケーブルにこだわる際だけでなく、オーディオ全般にも関わることで、消費者たるユーザーがどのようなスタンスでオーディオに望むのかということにも連環すると思います。この点について思うところを述べるのは、また別の機会に譲りたいと思います。
私は聴いたことがないのですが、ベルデンの8460というのはインターネットで見る限り、シンプルでありながらプロ使用ということで、やはり突き詰めていくと、簡潔で付帯を省いたものに収斂されるということなのかもしれませんね。
続いて、日本のガレージメーカーの雄、47研の木村さんに『晩夏のケーブル討論!』に加わって頂きます。メールと電話でインタビューした模様をご本人に了解を頂いた上で掲載いたします。
■メールでのインタビュー
******************************
先ず10年ほど前のものですが、読んでください。
http://www.kcn.ne.jp/~m-yoshii/aa2/teramura.html
所々文字化けしてるかも知れませんが
●
続き
ケ-ブル類の比較試聴の時
1)接点部分を充分綺麗に磨いてから接続したか
2)A線とB線の長さは同じだったか
3)A線とB線は同じ所を通ったか
→(注)ケーブルAとケーブルBの長さが異なる際に、例えばAは地面に接地し、Bは空中接線となれば、条件が一緒とは言えない(例えば振動、例えば地磁気の影響)
4)プラグを含めた評価なのか
5)純粋にケ-ブルの比較するので有ればプラグも当然同じでなくてはいけない、もっと厳密に言えばハンダ付けを伴う場合はハンダの量、半田こてを当てていた時間、例えば6Nとか8Nとか言っても熱を加えれば4Nになってしまうこともある
→(注)プラグを半田付けする際に熱が加わるので、材質に変化を生じさせる
等々比較試聴はケ-ブル類に限らず条件を揃えなければ無意味です、とはいっても条件を揃えるのはきわめて困難です。
世の中にはケ-ブルが売るほど有るから、買ってきたり借りてきたり、ちょっと繋いで見ただけで直ぐAが良いとかBの方がよいとか判断する傾向がある、しかも個人のレベルならともかく文字になったときは影響が有るから読む側も気を付けねばいけません。
木村
******************************
(注)注記は電話でやりとりをした際に確認したもので、補足として付記したものです
■電話でのインタビュー
******************************
-そもそも何故ケーブルを変えると音が変わるのでしょうか
【47木村さん】線材固有のキャラクターだけでなく、被覆の違いも音の相違を生みます。またそればかりではなく、金属に代表されるプラグによっても、良かれ悪しかれ音の違いを発生させることになります。
-今ではケーブルによって音を変え、調整するということが一般的になりました
【47木村さん】そんなにケーブル、ケーブルと言うのもいかがなものか、と思ったりはします。あくまでも、そもそもの音を作っているのはアンプやスピーカー、プレーヤーというコンポーネントであることは昔から変わりません。
ただ、ユーザーの楽しみを奪ってしまったメーカー側の責任ということもありますので、一概にケーブルで自分なりに音作りを楽しむということを否定もできないし、これは個人の自由だと思います。
-メーカーサイドの責任というのは、具体的にはどのようなことでしょうか
【47木村さん】CDプレーヤーのブラックボックス化が挙げられると思います。レコードからCDへとメディアが変わり、あわせてCDプレーヤーのブラックボックス化が進みました。つまりレコードプレーヤーのようにユーザーが「いじって楽しむ」要素が消えていき、聖域化してしまいました。ここで登場するのがケーブルです。ユーザー個人の楽しみを提供することがコンポーネント側になくなったので、やむなくケーブルがその役割を担うこととなったのだと思います。
-木村さんの作ったケーブルは、髪の毛のように細い導体という特徴がありますが、どのようなきっかけで製品開発をすることになったのですか
【47木村さん】ケーブルに注目が集まるようになった当初、私はあまりハイエンドのケーブルというものに関心が湧きませんでした。なぜかと言えば、アンプの内部の線やピンジャックやプラグにどのような材料、素材が使われているのかという議論を置き去りにして、機器をつなぐケーブルにばかり目を向けることは滑稽に思えたからです。今から10年以上も前の話ですが。
色々なケーブルを試聴していく中で、一緒に開発をしていた人間から電話線が送られて来ました。オーディオ用の製品ではありませんが、これが非常に音質も良く、ユニークだと感じました。
つまるところ、電話線は人の声の帯域に関するノウハウがつまった電線だったのです。従って、これをオーディオに転用することには理があると思いました。そもそも黒電話の時代に開発された電話線は、旧電電公社の時に細かな規格が設けられたものです。銅線の洗浄に関して手間がかかっていて、線の撚り方にも独自なものがあります。コンマ4mmの電話線とコンマ5mmのLAN用の線では、その差はコンマ1mmしかありませんが音質には差異があり、電話線の方が上でした。人の声という帯域に対する何らかの処理がなされているのだろう、と。
そこから自社のケーブルの開発、製作が始まったという訳です。
******************************
PR
前回のブログで『晩夏のケーブル討論!』と銘打ったのですが、残念ながらコメントをお寄せ頂いておりませんので(>_<)、まずはメーカーを代表してTMD社/畑野さんからのコメントを改めて掲載いたします。
******************************
電源
電源ケーブルで音が変わるなんて、70年代ではまず誰も考えなかった事ですね。
でも、今ではオーディオに係わる人の中では常識ですし、先日も秋葉原の某店で雑談した折りに聞いたことですが、なんだかんだいってもオーディオ店では電源回りがコンスタントに動いているとのことでした。
考えれば、100VのAC電源は家庭用の汎用電力源として、当初は電灯線の呼び名の如く電気が点けばまず目出たいということで、その後、我が国の文化生活が豊かになるにつれ、その電灯線(つまり電球のソケットの事)からアダプターを介して炊飯器とかに電力を供給していた時代も覚えています。
壁に立派に汎用として電源が備えられるようになったのも考えてみればそんなに昔ではないわけです。
一極集中的にそのコンセントにつなぐ機器数が増えていき、いつしかオーディオ機器も仲間入りをするようになったというわけで、決して音質重視などではなく実用本意の設計だったと思います。
しかし、そんな事情の電灯線の壁コンからオーディオ機器にひくほんの1〜2mのケーブルで音が変わるのですから面白いと言えば面白いことですね。
ほんとうに音は奥が深いし、オーディオも奥が無限にありそうです。
******************************
(注1)読み易いように、句点と改行に限って加筆させて頂きましたこと、コメントの一部を割愛させて頂きましたことを記しておきます。
(注2)今回、生まれて初めて絵文字を使ってみました(^o^)v
あ、これ(+。+)~~なんだか( ´∀`)くせになりますなあ(ο^v^ο)
【現在のオーディオシーンにおけるケーブルの隆盛】について、皆さんのご意見をお聞かせ頂きたく、コメントをお待ち申し上げます。
と申しますのは、『そもそもケーブルで音が変わるということをどのように捉えればよいのか』ということについて、私は門前の小僧がゆえ、自分の中で考えやスタンスがクリアになり切っておりません。
先のブログにも書きました通り、電源ケーブルやピンケーブルといったオーディオケーブルを変えることで音が変化し、自分の好みにあったものをチョイスするというのは、これはとても愉快で楽しいことです。
しかし面白いと同時に、
(1)そもそもどうしてケーブルを変えると音が変わるのか
(2)また、なぜケーブルによって音を変えて、調整する必要が出てくるのか
(3)オーディオ雑誌の二大巨頭といえる『オーディオアクセサリー』誌には、その名の通り、ケーブルを吟味することが大切だと多くの紙面が割かれ、かたや『ステレオサウンド』誌にはさしてケーブルにまつわるテーマは登場しない。
それぞれ媒体に持ち味、特徴をもたせる必要があるとはいえ、ケーブルを適切に選択することがコンポーネントにとって必要不可欠なのであれば、SS誌だってケーブルについて取り上げるべきだろう。
ただ逆に、大概の場合、ケーブルよりもコンポーネントの方が値が張るのだから、AA誌の言うほどケーブルを重視しなくても良いのではないか
(4)もしかすると、専門誌とオーディオ流通店がタッグを組んで『ケーブル幻想文化?』を作り出して私を騙そうとしているのはないか(笑)
といった疑問があるのですが、疑心暗鬼になっても仕方がありませんので、凄腕ユーザーたる拙ブログをお読みの皆さんにお考えを伺おうと考えました。
あわせて、メーカーの方にも上記についての視座を、知り合いのよしみということでお尋ねして、本ブログに掲載しようと考えております。
と申しますのは、『そもそもケーブルで音が変わるということをどのように捉えればよいのか』ということについて、私は門前の小僧がゆえ、自分の中で考えやスタンスがクリアになり切っておりません。
先のブログにも書きました通り、電源ケーブルやピンケーブルといったオーディオケーブルを変えることで音が変化し、自分の好みにあったものをチョイスするというのは、これはとても愉快で楽しいことです。
しかし面白いと同時に、
(1)そもそもどうしてケーブルを変えると音が変わるのか
(2)また、なぜケーブルによって音を変えて、調整する必要が出てくるのか
(3)オーディオ雑誌の二大巨頭といえる『オーディオアクセサリー』誌には、その名の通り、ケーブルを吟味することが大切だと多くの紙面が割かれ、かたや『ステレオサウンド』誌にはさしてケーブルにまつわるテーマは登場しない。
それぞれ媒体に持ち味、特徴をもたせる必要があるとはいえ、ケーブルを適切に選択することがコンポーネントにとって必要不可欠なのであれば、SS誌だってケーブルについて取り上げるべきだろう。
ただ逆に、大概の場合、ケーブルよりもコンポーネントの方が値が張るのだから、AA誌の言うほどケーブルを重視しなくても良いのではないか
(4)もしかすると、専門誌とオーディオ流通店がタッグを組んで『ケーブル幻想文化?』を作り出して私を騙そうとしているのはないか(笑)
といった疑問があるのですが、疑心暗鬼になっても仕方がありませんので、凄腕ユーザーたる拙ブログをお読みの皆さんにお考えを伺おうと考えました。
あわせて、メーカーの方にも上記についての視座を、知り合いのよしみということでお尋ねして、本ブログに掲載しようと考えております。
オーディオユニオンのストアブログを見ていたら、オルトフォンの廉価な電源ケーブルが出ていたので買い求めた。PSC-3500XGシルバー。名前は大仰だが、中古で約1万円だからとても財布に優しい。思えば1ヵ月半くらいまえに電源ケーブルの“U-19”的代表選手、PSC-4500というのを取り入れようと考えたのだった。(→7月6日付けブログ『良きチームに良きスカウトあり』)
"3500”と“4500”。まあ大体一緒ではないか。乱暴ではあるが、そう考えた。いや考えることにしたのだ。そのくらいの丼勘定は仕事で慣れっこである。ユニオンのS氏はやや不安そうな顔をしながら、試聴してもらって構わないなどと言うが、流石にド素人の僕でも1万円という値段の電源ケーブルを借りることは、ユニオンに失礼なのではないかと思った。だから買ったのであるが、S氏の悪い予感は見事に当たった。
マイルスのトランペットは、ペラペラと薄っぺらく耳障りになってしまった。いくらなんでもこれはまずい。我が布陣に適していないのは明白だった。今回のテーマはフォノイコの電源ケーブルである。
どこの誰に頼るか。TMDのホームページを見ると、一体これでこの夏何回目かというサマーセールを開催していた。電源ケーブルで廉価なやつがいくつも出ている。この助け船に乗ることにした。値段が安いからといって、適当にチョイスすると手痛い目に逢うことを学習したので、TMDの畑野氏に電話をしたところ、親切に相談に乗ってくれた。誠にもってユーザーフレンドリーな会社だ。ガレージメーカーとはいえ、消費者や読者から入る問い合わせに、いちいち答えるというのはとても骨の折れる作業である。
畑野氏によれば、フォノイコは情報量の多いアンプであって、単線が良いのではないかという。オルトフォンの3500はおそらく単線ではないのではないか、との指摘もあった。オルトフォンは銀線を使っているから”シルバー”の名を製品名に入れていることは分かっても、撚り線なのか単線なのかは知らなかった。ユニオンに技術的な説明を求めるだけの知識、教養を持っていないことは、誠に悲しい。だが、途方に暮れるばかりでも仕方がない。
畑野さんに3種類の電源ケーブルを送ってもらうこととした。以下に僕なりの拙い『翻訳』を記す。(※『翻訳』→8月27日付けブログ『不実なパワーアンプか貞淑なプリアンプか』)
▼電源ケーブル
【TMD】
・EARLY AC CABLE(1.5m)/ミリタリー的な色合いなので、以下『老兵』と略す
・超初期型(2m)/プラグにピンクを配しているので、以下『初老の恋』と略す
・NEW AG/平成11、12年あたりの製品とのことなので、以下『入社6年目』と略す
(左前=『老兵』、右前=『入社6年目』、中後ろ=『初老の恋』
▼試聴盤(LP)
①カーペンターズ/ベスト盤/『クロース・トゥ・ユー』
②マイルス・デイビス/リラクシン/『イフ・アイ・ワー・ア・ベル』・『ユー・アー・マイ・エヴリシング』
そもそもオルトフォンは我が家では歪感があって、マイルスだけでなくヴォーカルも薄っぺらだった。繰り返しになるが、これが解決すべき課題である。
まずはカーペンターズを聴く。
『老兵』は、あくまでも楽曲の中心にあるのはカレンの歌声であることを主張する。真ん中に凝縮している感じだ。そして、しっかりと、かちっと歌姫の声を描写する。『初老の恋』は、僕が名付けたからなのか、とても優しい。そのかわり、『老兵』に比べて中心感は薄らいだ。全体を鳴らそうという意図もあるようだ。『入社6年目』は、『老兵』と同様に歌声が中心にある。艶かしい感じさえする。最もはっきり、くっきりとする。『老兵』と比較すると現代的で綺麗な印象で、ケーブルの個性は和らいだ。一番面白いと感じ、最適解に近いのは『老兵』だった。
マイルスに移ると、『老兵』はさらに威力を発揮した。ミュート・トランペットは”端正”ともいえる再生音となった。楷書的とも評されるカートリッジのDL-103とのマッチングもいいように思う。
これは彼(老兵)に決まりだ!
勝負は決してしまったが、順序を変えて『入社6年目』をつなぐと、マイルスが艶っぽく水に濡れた感じが出て悪くないのだが、耳をつんざくようなピーキーさもある。トランペットのアタック感が強い気がする。ガーランドのピアノの快活さにも合っているのだが、やや腰高だ。『初老の恋』は、名前の通り”落ち着き”がある。”つんざく感”は『入社6年目』に比べて少ない。荒れた心をスタビライズするには良いかもしれない。
思えばTMDのウェッブにも、畑野さんへ電話した折りにも、『老兵』の実力は折り紙つきであるということなのだった。技術的なことはよく分からないが、フォノイコは東京サウンドのPE100SEという機種で、NFBをかけずに周波数帯によって歪率が変化しないCR型としている。畑野さんが、周波数帯を整えてやることが”うんたらかんたら”と述べていたような気もする。だから両者は適合したのであろうと想像する。
TMDのケーブルは楽しい。マニアックな要素を多分に秘めながら、子供の頃に夢中になったスーパーカーのようにラインナップが豊富で、レアものというか希少なモデルを時に入手することもできる。それぞれの製品にバックストーリーや特徴を持たせる工夫もうまく、業界で独自のポジションを得ている訳だから、大手のメーカーは見習うべき点も多いのではないか。
予算のことは別として、Sugarさんの賞賛するカルダスのゴールデンパワー(←※リンク張付け)という輩に興味津々だったが、よく思い起こせば、我がオーディオの陣容はフォノイコと47アンプをつなぐワイヤーワールド以外は、全て”日本人”揃いだ。誤解を恐れずに申し上げれば、僕は”オーディオ国粋主義”を推進しているのである。しかも没個性な大資本に頼ることを避け、小さいながらも個性豊かなメーカーの製品を積極的に登用している。外国語が不自由なため取材をする際、”日本語を話す人“が製品を作っていることも勝手がよい。いずれ卒業、転向して欧米列強国製品の軍門に下る時がやって来るのかもしれないが、いまはTMDやら47研やらコニシスやら、向こうは嫌々なのかもしれないが、電話をすれば何とか楽しいやりとりをすることのできるガレージメーカーに心惹かれているという訳だ。
●
CDプレーヤーにもつないで検証してみました。こちらは『入社6年目』に落ち着きそうです。これでピンケーブルとともにTMDで揃えることになります。(→8月4日付け『駄耳によるRCAケーブル試聴記』)
空中ケーブルサーカスの図。こういう風景をふと客観的に見ると、一体何をしようとしているのか自分でも分からなくなって来ます・・・。
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
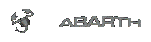
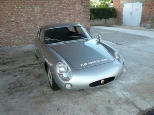
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
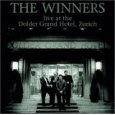
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
