×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
まだまだやるべきことが山積みである。オーディオの話だ。何となく落ち着きつつある現況のシステムではある。この“現状をキープしよう”というコンサバティブな性根というのは、大人の世界では受け入れられやすい志向ではあるが、理想郷へと至る暗夜行路では邪魔となるものだ。棘(いばら)の道をあえて歩くのは、現状を打破し続けたいという欲求があるからであって、それこそが荒地を分け入っての進軍を支えるのである。装備は少ない。細腕かもしれない。頼りは、まだ誰も見たことのない景色を眺めたいという気持ちだけだ。“なぜあんな恐ろしい生死の境の中に生きる事を僥倖しなければならない運命にあるのだろう”(有島武郎『生まれいずる悩み』)。
大風呂敷を広げたが、内実はたいそうなものではない。コンポーネントの更新もしたくてたまらないし、静寂の間の調音だって事足りている訳ではない。フランスのFREA・CUBE(黒)という吸音材を使って、部屋のコーナーに沈殿しようとする低音を処理している。対のスピーカーの中央にもFREAのCarreレギュリエ(チャコールグレー)を置いていて、うまく真ん中に音は集合するが、いかんせん30cm角の吸音材では音のまとまりが何とも小さい。できれば、例の難解至極なフラクタル関数を応用した、拡散吸音反射材であるQRDのディフューザーかディフラクタルを設置したいと前から思っていた。ただなかなか値も張るので、先ずはFREAで応急処置を施しているのである。
ただ、吸音材製品は深刻なデザインデッドな状況にある。インテリアとしての機能を果たすのは、まことにFREAくらいなもので、他社品についてはまあ見た目は度外視して、先ずは音をきれいに調整しますからインテリアとしてどうこうなんて言わないでちょ、みたいなものばかりだ。だから自ずと雑誌などに出てくるマニアのオーディオルームというのは総じて趣味があまりよろしくない。弩級のプロダクトが並んだ圧巻の光景も、引きで全体を撮るとあれれということになりかねない。そんなにお金をお持ちならば、ちょっとだけでいいんでインテリアにも回してはいかがでしょうか、と言いたくなる。僕だって人のことを言えた義理ではないけれど・・・
●関連ブログ(過去ログ)
『インテリアとしてのBICYLE』
※6月7日付けブログ
PR
レフィーロ&アネーロでコニシスの新製品TYR1213、1214の試聴会が行われたので参加した。去る5月のハイエンドショーでお披露目し、人気を博したTYR1213、1214がついに発売を開始する。例の“赤いきつね”ならぬ“赤いアンプ”を作るコニシスである。前述のコニシス訪問時の試聴環境とは違って、レフィーロは完璧ともいえるルームアコースティクが施された“お部屋”である。こんなオーディオルームで音楽を聴くことができる人が日本に何人いるというのだろう。最高のシチュエーションで気になる製品を試し聴きして、いざ購入し自宅の“ウサギ小屋”みたいな6畳半の狭いスペースで音を出したら、“おい、この間聴いた音と違うでないの”とつい文句を言ってしまいそうである。何にしてもレフィーロの試聴部屋は、QRDの小難しいフラクタル関数を駆使した音響拡散パネルをふんだんに設置し、天井は上手い感じで凸凹が設けられるなど随分と手が込んでいる。
小西社長の司会進行のもとTYR1213と1214の音出しが始まる。当たり前かもしれないが、学芸大学の地下作業場で聴いた、解像度が高く透明感の溢れる音に変わりはない。録音モニター機の性格で、原音ソースへの余計な色付けはない。一言で言うと、僕はこのコニシスのアンプは、「実存感」のアンプであると思っている。ハイデガーやサルトルの実存主義アンプ。今ここに“ある”ということ、をこのアンプは最重要視している。
時にスタジオで録音作業をしていると、10時間とか20時間という長時間に渡ってミュージシャンが奏でる音を聴き続けることになるという。耳疲れ、聴き疲れをするアンプでは仕事にならない訳だ。また、歪みがないこと、位相が正しいことも重要だという。録音した生音にミキシングコンソールを使って、リバーブをかけたり、更に高音を伸ばしたりと“加工”を施しては、音を再生し確認する。
よく巷で“原音再生”などということが言われる。正確に言えばCDやレコードなどのパッケージとして商品となったソースを原音として忠実に再生するという意味で“原音再生”なのだ。“本来の音”とはもちろん、コンサートホールや録音スタジオで演奏された音そのものであり、次の段階ではレコーディングされたマスターテープの音であって、加工された商品としての音ではない。つまり我々が手にするパッケージメディアは既に原音ではなく、加工が施された音であって、これがオーディオ再生における“原音”である。決して“生音”ではない。ソニーロリンズがそこに居るように音を再生したい、というのは録音された生音に手を加えた加工音を持ってして、擬似的にまるでそこでテナーをブローしているように感じるというだけで、これはあくまでも脳の錯覚認知機能を使って雰囲気でそう感じるということなのである。オーディオ装置で音を再生する時に、何をして“原音”かということは重要である。CDやLPの音が原音なのである。
さて、話はそれてしまった。コニシスのTYRである。小西さんが気を配っていることに“低域の制御力”というものもある。スピーカーの振動板を、特に低音域でビシバシ統御するということだ。止めるべき時に止まる低音を目指した。これがゆえに、DCアンプを採用している。トランスを排除し、逆起電力を追放したのだという。僕は馬鹿でかいトランスを積んだ長方形デカ弁当箱式アンプが苦手なので、厚みが薄っぺらいアンプを見ると、“おお、巨大なトランスを積まないように工夫を凝らしているなあ、よしよし”と思ってしまう。更に上記機種であるCL-1やCL-2ではミリタリーグレードの部品を搭載するべく、自衛隊向けの部品メーカーへ発注したとかしないとか。やはり、研究所を社名に冠するだけのことはある。完璧な再生装置など存在しないが、“いまそこにある”ように音を鳴らすコニシスアンプは、アンプ製作者のスタンスとプロダクトがともに明瞭かつクリアーである。
●続きはこちら↓
<6月10日付けブログ>
コニシスアンプとウィルソンスピーカーの邂逅
●過去のブログ↓
<6月3日付けブログ>
コニシスについて
寒さも和らぎ春めいて来た4月の初め、コニシス研究所を訪れた。学芸大学駅の商店街の外れに居を構えるコニシスだが、会社の所在地である住所に辿り着いてもなかなか見つからない。一見分かりにくい看板を見つけ地下へ続く階段を下りていくと、そこにコニシスのスタジオ(studio)=工房がある。
社名に”研究所”を冠する。研究とは何なのか、広辞苑(第5版)によれば、物事をよく調べ考えて真理をきわめること、とある。真理を希求することは、これすなわち理想を追い求めることである。エイズや癌や水虫を治す万能の薬を創り出すのも研究ならば、理想の再生音をオーディオコンポーネントから紡ぎ出すのも、もちろん研究だ。僕は研究というものを敬服している。理想に到達しようというその姿勢、スピリットが無条件に好きなのだ。普段何とはない日々を送っていると、世の中は理想に反するような事柄ばかりのように思える。だから、何とか世の潮流に抗って物事のありのままの姿を捉えることを目標に掲げる人間に好感を持っている。
しかし、僕の知る研究所を主催する人達はみな、いい意味で肩の力が抜けていて、社会との関係を断って仙人のような暮らしをしながら山に籠って研究に打ち込むタイプではない。いつもは社交的な、まあどこにでもいそうな「いいオヤジ」だ。ただ共通しているのは、一皮剥いた時に現れる強烈な自意識と理想に向かっているという高いプライドをみな持っているということだ。その矜持を持っていない“エセ研究者”など当たり前なのだが僕は認めなし、興味もない。
コニシスは今から20年以上前、業務用の音響機器の製作を生業とする自分達のためにアンプを作ったことからオーディオメーカーとして出発した。スタジオなどに向けたプロ機の製作を行うとともに、レコーディングスタジオを設けて録音事業も展開している。いや社業としてはむしろこちらがメインストリームなのかもしれない。
代表の小西さんは、レコーディングエンジニアとして実務をするばかりか、自らアンプの回路設計を手掛ける。社長がアイデアを書き起こし、実際に製品としてまとめ上げるのは部長の川村さんの仕事だ。小西さんは言う、国内外のハイエンド製品は音が“作られている”部分が多く、そこに多大なコストがかかっている、と。それを認めないという矜持の狭さは持ち合わせていないのだけれど、法外な値段のハイエンド民生機に対するアンチテーゼということは充分に意識しているようだ。フラッグシップとなるCL-1、CL-2(プリ、パワー)は、もちろんグレードも価格もハイエンドに準ずるクラスだが、マークレビンソンの名機にインスパイアーを受けた小西さんとしては、是非取り組みたい基幹機種であった。
実際に音を聴かせてもらうと、やはり録音スタジオを営むメーカーの製品だけあって、解像度が高く、透明感に溢れていて“ソースをそのまま鳴らす”という方向で機器が作られているように感じる。ただ試聴環境としては、その辺の倉庫といった風情で、スピーカーの後ろ側は剥き出しのコンクリートで、あまり良いものとは言えなかった。だが、それは予めこちらがお願いしてのことだったので、何の戸惑いもない。むしろ、ルームアコースティックの施された良好な環境で聴いたら、もっと凄い音になるに違いないという期待の方が大きい。
先ず僕が目の当たりにしておきたかったのは、コニシスの仕事場であった。仕事机を見れば何となくその人の仕事の仕方なんかが分かってしまうのと一緒で、工房を見学すれば、その製品がどんな音で鳴るのか、どんなことを考えて作り上げられたのか垣間見れるというものである。沢山の録音機材が設置されたスタジオは、まさに音響のプロの世界そのものであった。
録音スタジオを持ち、自分たちのレコードレーベルもあって、業務用と民生用のプロダクトを製作するという世界でも稀有なオーディオガレージメーカーとして、コニシスへの関心を背けずにはいられない。
かつて煙草を呑むということは、大人の嗜みでありました。祖父の家に行くと、食卓の大きな平机の真ん中に透明なクリスタルの灰皿が置いてあって、美味そうに煙を燻らせていた姿を思い出します。「おじいちゃんの家」といえば、紫煙が立ちのぼり、そこかしこの置物に染み込んだ煙草の臭いが小さな頃は思い起こされました。いま思えばとても体に悪いことでだったのでしょうが、副流煙をかき集めて大人が煙草を吸う真似事をしたものです。祖父のマイルドセブンが切れればすぐ近くの自動販売機に買いに行くのが僕の役目でした。たくさんある銘柄から間違えることなく持って帰ると、褒められて嬉しかった記憶があります。
かつて子供と大人を分ける分水嶺の一つが煙草でした。夏になると、花麦わらのストローハット(カンカン帽)を被って、着流しの内袖に煙草を忍ばせて上野公園まで散歩に連れて行ってもらいました。腕に巻かれた金時計とか、ヘアトニックなのかオーデコロンなのかは分からなかったけれど、微かな芳香を携えた祖父に「大人」を感じたなあ。
いまでは煙草は単なる悪者です。隅っこに追いやられ、肩を窄めて隠れるようにして煙を吸う毎日。禁煙ファッショである。確かに近日の健康科学によって喫煙行為は健康を損ねる可能性の高い嗜好品であることは自明のものとなり、他人へ迷惑をかけないよう愛煙家は気を配らなくてはなりません。でも、かつて煙草は文化であり、大人の嗜みでありました。何も急いて追放するばかりでなくてもいいのに、と思うのですが。
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
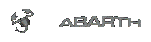
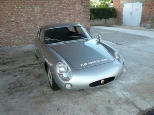
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
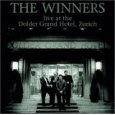
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
