■●音楽コンサート評
[2025/02/02] [PR] (No.)
[2008/07/19] ●[28]『北欧音楽の調べVol.5東方への憧れ』 (No.146)
[2008/05/25] ●[25]ファンク・オールスターズ来日コンサート (No.135)
[2008/04/21] ●[24]オイスタイン・ボーズヴィーク(Øystein Baadsvik)来日コンサート (No.128)
[2007/11/06] ●[17]生演奏の愉しみ ーミッシャ・マイスキー来日公演― (No.90)
[2008/07/19] ●[28]『北欧音楽の調べVol.5東方への憧れ』 (No.146)
[2008/05/25] ●[25]ファンク・オールスターズ来日コンサート (No.135)
[2008/04/21] ●[24]オイスタイン・ボーズヴィーク(Øystein Baadsvik)来日コンサート (No.128)
[2007/11/06] ●[17]生演奏の愉しみ ーミッシャ・マイスキー来日公演― (No.90)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
先週の日曜日に、仕事で神谷町に出かけ、足早に初台のオペラシティーへと向かい、ステーンハンマル友の会が主催するコンサート『北欧音楽の調べ』を聴きに行った。
ステーンハンマルをはじめとして、スウェーデンの作曲家が中国や日本、中東などをモチーフに作曲したものを演奏。選曲に工夫のあるコンサートだった。こちら極東アジアの日本から北欧をイメージするのと同じように、北欧人がオリエンタルを題材にするとどんな曲になるのだろう、という興味を満たすプログラムだった。
会を主宰する和田氏のインタビューが『音楽之友』誌7月号に掲載されている。
W.ペッテション=ベリエル:ノルランド風ラプソディ
H.ルーセンベリ:「14の中国の詩 」より
H.ルーセンベリ:主題と変奏
E.シェーグレン:月光の中の階段
S.フォン・コック:蓮の花
G. ド・フルメリ:「4つの中国の歌」作品66
A.アッテルベリ:組曲 第1番「オリエンタル」(Pカルテット版)
W.ステーンハンマル:ランプのアラジン王子
M.カルコフ:4手の為の「東洋の絵」 作品66d
M.カルコフ:10の日本のロマンス 作品45
W.ペッテション=ベリエル:オリエンタル・ダンス (編曲:和田記代)
ステーンハンマルをはじめとして、スウェーデンの作曲家が中国や日本、中東などをモチーフに作曲したものを演奏。選曲に工夫のあるコンサートだった。こちら極東アジアの日本から北欧をイメージするのと同じように、北欧人がオリエンタルを題材にするとどんな曲になるのだろう、という興味を満たすプログラムだった。
会を主宰する和田氏のインタビューが『音楽之友』誌7月号に掲載されている。
W.ペッテション=ベリエル:ノルランド風ラプソディ
H.ルーセンベリ:「14の中国の詩 」より
H.ルーセンベリ:主題と変奏
E.シェーグレン:月光の中の階段
S.フォン・コック:蓮の花
G. ド・フルメリ:「4つの中国の歌」作品66
A.アッテルベリ:組曲 第1番「オリエンタル」(Pカルテット版)
W.ステーンハンマル:ランプのアラジン王子
M.カルコフ:4手の為の「東洋の絵」 作品66d
M.カルコフ:10の日本のロマンス 作品45
W.ペッテション=ベリエル:オリエンタル・ダンス (編曲:和田記代)
PR
『ファンク・オールスターズ』が来日し、東京ミッドタウンのビルボード東京で23日、ライブ演奏を行った。ファンクの帝王、ジェームス・ブラウン(JB)のステージを支えた、フレッド・ウェズリー(トロンボーン)、ピー・ウィー・エリス(テナーサックス)のホーンセクションに加えて、ハモンドオルガンの大御所、ロニー・スミスとロドニー・ジョーンズ(ギター)、アイドリス・ムハマド(ドラムス)というバンド構成。
1曲目は、落ち着いた感じのジャズファンク。来日後、初回のステージで慣らし運転なのであろうが、さすがにベテラン揃いだから、黒く粘っこくこなれた演奏。
2曲目はハンク・モブレー・セクステッド『タッチ・アンド・ゴー/touch and go』をファンクの味付けをして披露。トロンボーンもテナーも、ソロは完全にジャズのコード進行。ドラムがファンクらしいビートを刻む。バンドにベースがいないのに、通奏低音が聴こえて来る。よく見ると、贅沢にもロニー・スミスがベースラインを奏でている。ハモンドのB3と思しきオルガンの上に、コルグのシンセサイザーかシーケンサーがひょこっと乗っていた。これでベースの音に変換していたのかもしれない。ハモンドオルガンならではの音をもっとソロで弾いて欲しかったが、おそらくベーシストが事情があって帯同できなかったのであろう。
3曲目はビートルズの『カム・トゥギャザー』。照れ隠しのような笑いを携えて曲を紹介。日本人には馴染みの深い曲であり、会場もやおら盛り上がって来た。
4曲目にやっとJBと思しきナンバー。観衆は待ってましたとばかりに、手拍子を始め、ビートに合わせて体を揺らし出す。ファンクというのは人を楽しませる音楽だ。事前に演奏の曲を知らなくとも、自然と笑顔がこぼれる。
昨年の冬に、同じくファンクバンド『ウォー(WAR)』のキーボード奏者、ロニー・ジョーダンのステージ( ※11月20日付けブログ『●[18]ロニー・ジョーダン来日コンサート』 )でも感じたことなのだが、ファンクの手練はジャズを弾かせても実に上手い。そしてまた、JBのファンクナンバーを期待していたファンには、物足りない感じになってしまう。私は個人的にはジャズもファンクも両方いける口なので満足するのだが、ジャズの曲はいいからファンクばかりで構わないという人の方が本ライブでも多かっただろう。
いずれにしても、ビルボード東京を初めて訪れれば、これは必ず驚くはずだ。ステージの後ろの窓ガラス越しに、六本木ミッドタウンの夜景が一望できるからだ。行ったことはないが、さながらニューヨークマンハッタンの高層ビルの中のようなアーバンな洒脱さを持つライブ会場だ。8月に1周年を迎える。
聞き慣れない名前かもしれないが、ノルウェー人チューバ奏者のソロコンサートに行って来た。
いや、驚きましたね。
「金管楽器ってこんなこともできるんだ」という具合で、マウスピースと口を上手い具合に少し空けてヴォイスパーカッションのような音を出したり、モンゴルのホーミーみたいな音色でチューバの音に声が混ざっている演奏あり、と驚き唸った次第。
こんなのサックスやトランペットやトロンボーンでは聴いたことがない。音楽ジャンルもクラシックだけでなく、ジャズでは06年の『東京JAZZ』に来て、チックコリアと競演したというし、演奏ナンバーにはピアソラも入っているし、アイデアが豊富なのだ。海外のメディアもその超絶技巧には脱帽のようで、今後ますますの活躍を期待したい。
コンサートの前に音大生向けのマスタークラスがあったのだが、こういうのを見る機会もないので面白かった。音大生とオイスタイン氏とで、明らかに誰が聴いてもレベルの違いがあることが分かって、やっぱりプロはプロだと妙に納得した。
●読みにくいかもしれませんが、自身のHPアドレスの下に、「日本6回目来日、日本食が好きです」と漢字で書いてくれた。お茶目な人ですね。

※著作権はØystein Baadsvik氏に帰属します。
※公式HP:www.baadsvik.comで公開されています。

いや、驚きましたね。
「金管楽器ってこんなこともできるんだ」という具合で、マウスピースと口を上手い具合に少し空けてヴォイスパーカッションのような音を出したり、モンゴルのホーミーみたいな音色でチューバの音に声が混ざっている演奏あり、と驚き唸った次第。
こんなのサックスやトランペットやトロンボーンでは聴いたことがない。音楽ジャンルもクラシックだけでなく、ジャズでは06年の『東京JAZZ』に来て、チックコリアと競演したというし、演奏ナンバーにはピアソラも入っているし、アイデアが豊富なのだ。海外のメディアもその超絶技巧には脱帽のようで、今後ますますの活躍を期待したい。
コンサートの前に音大生向けのマスタークラスがあったのだが、こういうのを見る機会もないので面白かった。音大生とオイスタイン氏とで、明らかに誰が聴いてもレベルの違いがあることが分かって、やっぱりプロはプロだと妙に納得した。
●読みにくいかもしれませんが、自身のHPアドレスの下に、「日本6回目来日、日本食が好きです」と漢字で書いてくれた。お茶目な人ですね。
※著作権はØystein Baadsvik氏に帰属します。
※公式HP:www.baadsvik.comで公開されています。
バッハの無伴奏曲の1、3、5番が演目であったが、序盤は音が小さくて、オーディオ装置で聴いていたならば音量のボリュームに手を延ばすところ。1週間前から地方を廻っていたようで、ややお疲れだったか。帯同した御仁いわく新宿オペラシティーは、ソロコンサートにはハコが大き過ぎると指摘。最後のアンコールあたりで、ようやく本領発揮の感あるも、時すでに遅くコンサート終了。
ただとても内省的な表現で、コアなファンの人たちはその姿を見て、「ああ、ラーゲリ(強制収容所)に入っていた時は大変だったのだろうなあ。いまは息子、娘と共演するようなことになって実によかった」とマイスキーの人生の表裏を演奏に重ねるのだろう。
僕は個人的には、「私のチェロを聴かせて進ぜよう」とか「俺様のトランペットを聴きやがれ」みたいなゾンザイな態度で「感じ悪いなあ」と思わせておいて、圧倒的な存在感やらテクニックやら表現力やらでこちらは叩きのめされ、平伏してしまうような演奏家が好みなので(何だかこう書くとマゾヒスティックな志向があると勘違いされそうですが)、やっぱりチェロであればマイスキーの師匠ともいえる近日逝去したロストロポーヴィッチの方をとりたい。近代の自我の爆発がごときバッハ無伴奏。神への畏敬よりも自己を発露することが勝ってしまうというのは、まさにモダンなるエゴである。
⇒関連ブログ『恐ろしき個の時代』
⇒関連ブログ『恐ろしき個の時代<その2>』
にほんブログ村 エッセイ・随筆
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
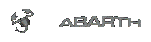
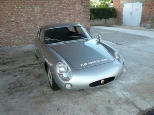
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
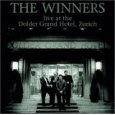
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
