×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
仕事で浜松に行っていた。お決まりではあるが、ウナギを食した。浜名湖の養殖うなぎである。なぜ浜名湖で養殖を始めたのか、なぜウナギだったのかなどはよく分からないが、インターネットでちらと調べてみるとウナギの生態そのものも謎に包まれている。
分かっていることと言えば、海で生まれ、河で育ち、産卵のために再び海に戻るということくらいのようだ。それぞれで過ごす歳月やどのくらい生きるのかさえ把握されていない。養殖ということは諸となる卵がある訳だが、天然のウナギの卵を見た人間というのも、これまた誰もいないらしい。
なんてミステリアスな生き物なのだ。どこで生まれたのか、そいつが何歳なのか、まるで象の死に場所のように誰も生まれ出ずる瞬間を見たことがなく、大量に人間どもに食われる。
なんて悲しい魚なのだ。そんな悲しきウナギに思いをはせながら、玩具が欲しくて仕方がない子供のように涎を垂らしながら、しばしの別れを惜しみ再会の喜びに抱擁するがごとく、レコードに針を落とした。
マイルスの『セブン・ステップス・トウ・ヘブン』だ。J-WAVEで土曜日の夜に放送している、『Make IT 21』という妙に声の格好が良い、自称コンサルタントがDJを務める番組のテーマソングになっているので、ついこのプログラムを思い出してしまって失笑する。それはさておき、この盤では移行期のマイルスがジャズクラシックスともいえる曲を演奏していて興味深い。迷いがあったのか、アルバムのセールスを鑑みて入れることになったのかは不明であるが、いずれにしても、タイトル曲のキャッチーなフレーズは耳触りがとても良い。エスニックな香りのする旋律は、ただアーシー(土着的)ということでなく、もちろんマイルスの洗練された様式美に収容されている。
2000キロ離れたマリアナ諸島からやって来て、何だかよく分からないのに味がうまいと言ってみなにバクバクと食べられてしまうウナギとまさかマイルスが同じだなんて間違っても言えないが、僕の世代にとってのジャズというのは、遥か昔の遠いところから見参した(実際はそんなに前ではないのだけれど)どうにも格好の良い音楽で、そんなに良くは知らないが食べたら最後、食べ方も調理法も様々でその魅力に魅了されてしまう音楽ではある。
PR
オーディオへの散財では、嫁さんにぶん殴られ、往復ビンタをかまされそうな気もするので、ビクビクしながら記す。
6月はボーナスシーズンである。金融機関が資産運用のキャンペーンを一斉に打ち出す。世に金が溢れ出すのと花嫁が結婚式をしたがることにどんな因果があるのかよく分からないが、いずれにしても消費をしたくなる”月”である(余談であるが、ちなみに保険会社は11月を保険月とするらしい)。バリバリと、いや謙虚にオーディオアクセサリーをぼちぼち買い込んでいる。
なかでも、嫁さんから「なぜ墓石を買うのか。自分用としてか。外のドライエリアに建立でもするのか」との責めを頂戴した、石匠運慶の天然御影石はなかなかに音が“ぐぐっ”と締まってよろしい。厚みが5cmで、一枚20kgもある。玄関から地下のオーディオ部屋へと運ぶのに、腰が抜けそうになる重量だ、“こいつは期待できる”。御影石が良いとアドバイスしてくれたのは、前述のオーディオユニオン4階のS君である。自分でも使っているという科白は、販売店員の“伝家の宝刀”だ。これを出されては、退転はできない。素直に従った。
我がオーディオルームはコンクリート打ちっ放しで、基礎たる床は当然コンクリートなのではあるが、その上に木材としては柔らかい部類に入るパイン材のフローリングが施してある。ちょっと重たいものを置いたり、乱暴に掃除機をかけたりすると、傷が付いてしまう。デリケートなのだ。であるからして、対策を講じる必要が多分にある訳で、オーディオアクセサリー誌でお褒めに預かっていたABAという新興メーカーの薄型ボードに、その推奨するKRYNAのマグネシウムインシュレーターをもってしてスピーカーを置いていたのだが、どうも低音の出が悪い。47研の小柄で小粋なスピーカー、Lensはフルレンジだから、ロウ(LOW)を厚く出来させるのは難しいのかもしれないが、“こんなもんじゃないだろうな、このスピーカーの実力は”と思っていた次第だ。
足場をがっちりと固めるということは、床が鳴かなくなる。さすれば、音が締まる。ただ気をつけねばならないのは、床が震えない以上、床をも鳴らして豪快に低音を出すということには、決別せねばならない。少しだけ迷ったが、やはり挑戦は必要だ。御影石で、バシッとした音にしようではないか。
苦労して自作したオヤイデの電源ケーブルともあいまって、音がちょっとノーブルになった気がする(プチ・ノーブルな気分!)。やはり散財しないと音の進化を遂げるのは難しいことかな。
この三つの照明は、いずれも1980年代の卓上スタンド式のものだ。地下の“静寂の間”は精神をスタビライズさせるための空間だから、いまどきのエッジの立ったデザインの照明器具は似つかわしくない。墨汁で塗られた黒い床とコンクリート打ち放しのシンプルなスペースは、何故だかとても柔らかな印象を与えてくれる。空間の構成要素としてはシャープであるにも関わらず、引き算の美学というか日本的な建築手法に近いからなのかもしれないが、簡素がゆえに迫って来る感じがしない。
僕が憑き神に追われるようにアナログレコードに精を出すのも、日常の由無し事にまみれてクタクタになった心をこの場で安寧に導こうというコンセプトから言えば自然なことだ。数値特性や技術的な進歩の度合いからすれば、明らかにレコードよりもCDの方が上であるはずなのに、音に“癒される”のはどうしたってアナログが勝る。音楽がしなやかで優しく聴こえる。マイルスの、あの激しい『フォア&モア』だって、空間のそこかしこに楔を打ち込んではいるけれど、聴いた後にささくれ立った心持ちは不思議と落ち着く。
そういう在り処だから、ポンコツでやれてはいるが、この昭和モダンな照明は心の奥底の薄暗いところもたおやかに照らしてくれる。
●関連ブログ(過去ログ)
『インテリアとしてのBICYCLE』
→6月7日付けブログ
●関連ブログ(過去ログ)
『ルームアコースティックとインテリアとしてのオーディオ』
→6月5日付けブログ
※やっぱり、こういう空間をさらっと用意する杉浦伝宗という男は、なかなかだと思う。やるなぁオデン。
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
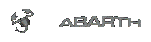
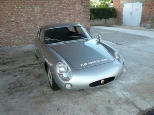
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
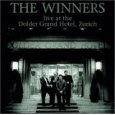
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
