■◆乱読日誌(書評)
[2025/02/02] [PR] (No.)
[2009/07/05] 『メディアの支配者(上下巻)』 (No.206)
[2009/05/31] 『官僚たちの夏』 (No.201)
[2009/05/31] 『ソニー最後の異端』-近藤哲二郎とA3研究所- (No.200)
[2009/05/24] 『考える人』(新潮社刊) (No.199)
[2009/07/05] 『メディアの支配者(上下巻)』 (No.206)
[2009/05/31] 『官僚たちの夏』 (No.201)
[2009/05/31] 『ソニー最後の異端』-近藤哲二郎とA3研究所- (No.200)
[2009/05/24] 『考える人』(新潮社刊) (No.199)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
フジサンケイグループの各社を受けようという学生諸子にとっては必読の書。内容はただ読んでみることを薦めるとしか私は言えない。現在は過去の延長線上にしかなく、未来は《いま》が積み重なった積層の上にしか存在し得ない、ということが雰囲気ででも分かっていれば、随分と入社以降に感じることにも違いがあるに違いない。
本書を通じて、メディア企業はよくも悪くも特殊な立場にあるということが分かる。あわせて『メディアの興亡』(文春文庫/杉山隆男)』、『新聞が面白くない理由(講談社文庫/岩瀬達哉)』、『渡辺恒雄 メディアと権力(講談社文庫/魚住昭)』、『「朝日」ともあろうものが(河出文庫/烏賀陽 弘道)』、『新聞社―破綻したビジネスモデル (新潮新書/河内孝)』などメディア、特に新聞社を取り上げた書籍も参考にされたい。
●
しかし今日は暑かった,,,テニスをしていて、『もうダメだぁ』と思ったら開始してから30分しか経っていなかった,,,サウナ風呂状態でした,,,プレー後のビール(ノンアルコールでも)がことさらウマかったけれど,,,
PR
城山三郎による代表作で、経済官僚ならば一度は読むといわれる小説。そのキャッチフレーズに興味を惹かれて手にしてみたら、これが面白い。こちらも一日半で読んでしまった。
読んでから分かったことがあって、一つは次のTBS日曜9時からのドラマがこの『官僚たちの夏』であるということ。主人公の「ミスター通産省」風越信吾は、佐藤浩一が演じるとのことだ。私にとってはタイムリーなネタであった。
そしてこちらの方が重要なのだが、登場人物にはそれぞれ実在の官僚のモデルがいるということだ。しかも主人公だけでなく、ライバルや部下も実際の人物から描き出されているのだから、小説というよりもノンフィクションかもしれない。経済官僚が一度は読む理由はそこであったかと腑に落ちた。
それから、経済小説の雄が実は執筆の苦しみにのたうち廻っていたということだ。『城山三郎伝 筆に限りなし』(加藤仁、著)の評伝に詳しいらしい。こちらも機をみて読んでみたい。
最近は文庫のページ数がやたらと減って、薄っぺらい背表紙の本が増えた。この『ソニー最後の異端』(講談社文庫/立石泰則)は通勤の電車40分で読み終わるかと思ったが、さすがに読了までは至らなかった。しかし二日あれば充分なのだが、内容が薄弱なことはない。近藤哲二郎というソニーの技術者の異端が、どのようにしてWEGA(ベガ)、そしてBRAVIA(ブラビア)の開発に貢献し、『DRC(デジタル・リアリティ・クリエーション)』というソニー独自の高画質技術を進化させていったか、そのルポルタージュである。
近藤はその性格から社内ではなかなか理解が得られず、400件もの特許をとりながら一つとして商品化されることがないという異端であった。当時、大賀典雄から異例の14人抜きで社長のバトンを受けた出井伸之は、近藤を呼んだ。そしてDRCのプレゼンテーションを受けた出井は近藤の起用を決意し、96年にはアルゴリズム研究所の所長に就任させた。
DRCはバージョンアップを重ねてゆくのだが、本書による技術詳細をかいつまめば、それは放送局から送られてくる映像を、高精細なものに置き換えるデジタル信号処理技術のことで、例えば標準放送をハイビジョン放送対応のテレビで見る時に、受像機としてのテレビは解像度を高めるために映像を補完する。いかに補うかといえば、線形補完形式と呼ばれる方法などがあるという。
これはどこかで訊いたことのある話だ。そう、WADIAのCDプレーヤーによるデジタル演算アルゴリズムだ。オーディオもビジュアルも同じようにエポックメイキングな技術、そしてそれを開発する<異端>によって切り拓かれてゆく。
●
この本を読んだ日にNHK『プロフェショナル 仕事の流儀』で、細野秀雄という材料工学の科学者を番組で取り上げていた。競争の激しい超伝導の分野で、世界から熱い注目を浴びる学者だという。細野は東工大の先生で、研究室のリーダー、舵取り役でもあって、「研究の現場に、立場や年齢による上下関係はない」ということを自負していた。穏やかそうな性格に見受けられたが、後進の指導シーンでは容赦はなかった。
近藤と細野。私には多分にだぶって見えてしまった。
新潮社から刊行されている季刊誌『考える人』の5月号。シーズン毎に発行しているのは、別にオーディオ誌だけではなかった。直近号のメイン特集『ピアノの時間』がよい。何がいいって、やっぱり吉田秀和と堀江敏幸の対談に尽きる。この組み合わせはNHK教育テレビの番組で行われてから何度か目にしている。それでも吉田秀和の話には蘊蓄があって飽きが来ない。音楽について「書くこと」(=吉田)、書かれたものを「読むこと」(=堀江)の愉しさに溢れている。音楽を作曲、演奏することに比べて、評論することが二次的、三次的だなんてちっとも思わないとか、グールドやら何やら、この人の手にかかると「今度そのアーティストのディスクを聴いてみよう」という気にさせる。ある意味で村上春樹と同じ、音楽を聴く気にさせる文章芸、話芸をお持ちだ。
その他、この雑誌を読んで思ったのは、1960年から62、63年生まれの大学にお勤めで、一般誌に発表をする腕に覚えのある人の執筆の場を提供しているのだな、ということ。いよいよこのジェネレーションが文壇の主たる地位を確保し始めていて、早晩この人たちが次なるメインを張ることになる訳だから、雑誌社としてこのアカデミズム作家達との関係を継続的に保つことは将来への確実な投資になる。文芸誌の凋落が叫ばれて久しいが、新潮社がいつまでこの『考える人』という雑誌を続けられるか、随分生意気なようであるが、応援しながら見守りたいと思う。
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
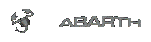
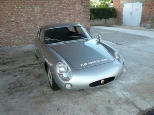
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
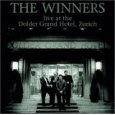
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
