×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
『ファンク・オールスターズ』が来日し、東京ミッドタウンのビルボード東京で23日、ライブ演奏を行った。ファンクの帝王、ジェームス・ブラウン(JB)のステージを支えた、フレッド・ウェズリー(トロンボーン)、ピー・ウィー・エリス(テナーサックス)のホーンセクションに加えて、ハモンドオルガンの大御所、ロニー・スミスとロドニー・ジョーンズ(ギター)、アイドリス・ムハマド(ドラムス)というバンド構成。
1曲目は、落ち着いた感じのジャズファンク。来日後、初回のステージで慣らし運転なのであろうが、さすがにベテラン揃いだから、黒く粘っこくこなれた演奏。
2曲目はハンク・モブレー・セクステッド『タッチ・アンド・ゴー/touch and go』をファンクの味付けをして披露。トロンボーンもテナーも、ソロは完全にジャズのコード進行。ドラムがファンクらしいビートを刻む。バンドにベースがいないのに、通奏低音が聴こえて来る。よく見ると、贅沢にもロニー・スミスがベースラインを奏でている。ハモンドのB3と思しきオルガンの上に、コルグのシンセサイザーかシーケンサーがひょこっと乗っていた。これでベースの音に変換していたのかもしれない。ハモンドオルガンならではの音をもっとソロで弾いて欲しかったが、おそらくベーシストが事情があって帯同できなかったのであろう。
3曲目はビートルズの『カム・トゥギャザー』。照れ隠しのような笑いを携えて曲を紹介。日本人には馴染みの深い曲であり、会場もやおら盛り上がって来た。
4曲目にやっとJBと思しきナンバー。観衆は待ってましたとばかりに、手拍子を始め、ビートに合わせて体を揺らし出す。ファンクというのは人を楽しませる音楽だ。事前に演奏の曲を知らなくとも、自然と笑顔がこぼれる。
昨年の冬に、同じくファンクバンド『ウォー(WAR)』のキーボード奏者、ロニー・ジョーダンのステージ( ※11月20日付けブログ『●[18]ロニー・ジョーダン来日コンサート』 )でも感じたことなのだが、ファンクの手練はジャズを弾かせても実に上手い。そしてまた、JBのファンクナンバーを期待していたファンには、物足りない感じになってしまう。私は個人的にはジャズもファンクも両方いける口なので満足するのだが、ジャズの曲はいいからファンクばかりで構わないという人の方が本ライブでも多かっただろう。
いずれにしても、ビルボード東京を初めて訪れれば、これは必ず驚くはずだ。ステージの後ろの窓ガラス越しに、六本木ミッドタウンの夜景が一望できるからだ。行ったことはないが、さながらニューヨークマンハッタンの高層ビルの中のようなアーバンな洒脱さを持つライブ会場だ。8月に1周年を迎える。
PR
最近またオーディオがとても楽しいです。小学生みたいな表現で恐縮ですが、ホントに尽きることがないですね、オーディオって、底なし沼です。
『GRFの部屋』さんのお宅へお伺いさせて頂いた時に拝聴したSTUDERは、B-62という型式だそうです。とにかくこれは見た目がカッコいい。更に音もいい。文句のつけようがないです。繰り返しになりますが、ノックアウト状態だった訳です。GRFさんが画像をアップされています。必見ですね。
今日の昼間は偶然UICORNさんと神保町でお会いして、2トラとか4トラとか図解して頂いたり、次に狙われているアナログプレーヤーとかアームとかカートリッジとか、他にもエラックのスーパートゥイーターなどについて、お話を伺いました。
先輩諸兄の<オーディオを楽しむ>スタンスというか熱意というか、頭が下がります。会話をさせて頂くなかで、これが大変勉強になっています。私は個人的には、大袈裟ですが、歴史や文化の継承、引継ぎを受けていると思っています。オープンリールもレコードも、我々の世代が知らないことを沢山知っていらっしゃる。
誰かが聞いておかないと、そのうち誰も知らないことになってしまうのでは、と思います。勉強が大の苦手である私が、こうして全然飽きないのは、オーディオはブラックホールのように奥が深くて、惹きつける何かがあるんですね。
理科は赤点以外取ったことがありませんから、電気のことや回路のことは、小学生並みの理解しかありません。また別に耳がいい訳でもないので、聞き分ける能力があるのでもなし。
そう思うと、どうしてこう面白いのかが説明できないですね。
それから、先日はある評論家の方と雑誌の企画で、いくつかの廉価版システムの音を聴く機会に恵まれました。こちらもこちらで、とても勉強になりました。ただいま進行中ですので、近々このブログでオープンできるのではないかと思います。私の試聴など当てにもなりませんが。
勉強が嫌いで、学生の頃や社会に出てからも、ろくすっぽ勉強してなかった訳ですが、いまはオーディオの<お勉強>が楽しいですね。苦しいことも、例えばお金がないとか、経験が浅いとか、もろもろあるのですが、いまは楽しさの方が勝っています。
『GRFの部屋』さんのお宅へお伺いさせて頂いた時に拝聴したSTUDERは、B-62という型式だそうです。とにかくこれは見た目がカッコいい。更に音もいい。文句のつけようがないです。繰り返しになりますが、ノックアウト状態だった訳です。GRFさんが画像をアップされています。必見ですね。
今日の昼間は偶然UICORNさんと神保町でお会いして、2トラとか4トラとか図解して頂いたり、次に狙われているアナログプレーヤーとかアームとかカートリッジとか、他にもエラックのスーパートゥイーターなどについて、お話を伺いました。
先輩諸兄の<オーディオを楽しむ>スタンスというか熱意というか、頭が下がります。会話をさせて頂くなかで、これが大変勉強になっています。私は個人的には、大袈裟ですが、歴史や文化の継承、引継ぎを受けていると思っています。オープンリールもレコードも、我々の世代が知らないことを沢山知っていらっしゃる。
誰かが聞いておかないと、そのうち誰も知らないことになってしまうのでは、と思います。勉強が大の苦手である私が、こうして全然飽きないのは、オーディオはブラックホールのように奥が深くて、惹きつける何かがあるんですね。
理科は赤点以外取ったことがありませんから、電気のことや回路のことは、小学生並みの理解しかありません。また別に耳がいい訳でもないので、聞き分ける能力があるのでもなし。
そう思うと、どうしてこう面白いのかが説明できないですね。
それから、先日はある評論家の方と雑誌の企画で、いくつかの廉価版システムの音を聴く機会に恵まれました。こちらもこちらで、とても勉強になりました。ただいま進行中ですので、近々このブログでオープンできるのではないかと思います。私の試聴など当てにもなりませんが。
勉強が嫌いで、学生の頃や社会に出てからも、ろくすっぽ勉強してなかった訳ですが、いまはオーディオの<お勉強>が楽しいですね。苦しいことも、例えばお金がないとか、経験が浅いとか、もろもろあるのですが、いまは楽しさの方が勝っています。
昨日、あるお宅で聴かせて頂いた音に、衝撃を覚えた。スチューダーのオープンリールデッキで再生された音だ。
これは次元が違った。あまりのインパクトで顎が外れて、話すのもやっとの状態だった。こんなに<芯>の詰まった音は聴いたことがない。フランク・シナトラやナット・キング・コールが真空管のマイクで歌って、コンサート会場の一番の席で聴くとこういう具合だったろう。
一体、技術の進化というのは何なのか。スチューダーの機械は1960年の半ばに製造されたものらしい。何のためにCDやデジタルオーディオは開発されたのか。音を良くするためではないのか。
私は自分のやっていることがひどくバカバカしくなるような空しささえ覚えた。
オープンリールはつまり、<オーパーツ>だ。
Out Of Place Artifacts、時代錯誤遺物。つまり、科学技術の進んだ後世からすれば、<出て来てはマズイ>遺物のことだ。プレ・インカ文明(紀元6~9世紀)のものと思われるジェット機とよく似た黄金細工。2000年前のペルーで脳外科手術を施したと思しき跡のあるシャレコウベ。現代の技術では作れないという古代マヤ文明の水晶のドクロ。
出土してしまうと理解や解釈が出来ないので、とても厄介だ。何より人々が恐れるのは、辻褄が合わなくなることだ。二千年前に脳外科手術をしていたら、これは本格的にマズイ。あまりに時代が早過ぎる。医療の技術がここまで進んだからこそ、やっとことさ頭蓋骨を開けて治療を施して、ということが出来るようになったのだ。
ライト兄弟が飛行機を発明する前に、インカ人やレオナルド・ダヴィンチが空を飛んでしまっていても都合が悪い。いまさら歴史の教科書を書きかえる訳にもいかない、「実はインカ人はナスカの地上絵を空から自分たちの飛行機で見ていました」と。
従って、オーパーツはたいがい、宇宙人もしくはムー大陸人の仕業かヤラセか捏造品ということで処理される。オーパーツというのは、「そもそも無かったんだよ、そんなもの」とか「見なかったことにしてさっさと忘れて、さあ平穏無事な日常に戻ろう」という代物だ。
私にとっても、初めて聴いたオープンリールデッキの音は、オーパーツであって欲しいと切に願っている。
大して考古学的な価値を見出されることもなく、歴史の教科書を塗り替えることなく、無難に忘れ去られるオーパーツ。
しかしそれは確かにそこに存在していたものなのだ・・・
にほんブログ村 エッセイ・随筆
これは次元が違った。あまりのインパクトで顎が外れて、話すのもやっとの状態だった。こんなに<芯>の詰まった音は聴いたことがない。フランク・シナトラやナット・キング・コールが真空管のマイクで歌って、コンサート会場の一番の席で聴くとこういう具合だったろう。
一体、技術の進化というのは何なのか。スチューダーの機械は1960年の半ばに製造されたものらしい。何のためにCDやデジタルオーディオは開発されたのか。音を良くするためではないのか。
私は自分のやっていることがひどくバカバカしくなるような空しささえ覚えた。
オープンリールはつまり、<オーパーツ>だ。
Out Of Place Artifacts、時代錯誤遺物。つまり、科学技術の進んだ後世からすれば、<出て来てはマズイ>遺物のことだ。プレ・インカ文明(紀元6~9世紀)のものと思われるジェット機とよく似た黄金細工。2000年前のペルーで脳外科手術を施したと思しき跡のあるシャレコウベ。現代の技術では作れないという古代マヤ文明の水晶のドクロ。
出土してしまうと理解や解釈が出来ないので、とても厄介だ。何より人々が恐れるのは、辻褄が合わなくなることだ。二千年前に脳外科手術をしていたら、これは本格的にマズイ。あまりに時代が早過ぎる。医療の技術がここまで進んだからこそ、やっとことさ頭蓋骨を開けて治療を施して、ということが出来るようになったのだ。
ライト兄弟が飛行機を発明する前に、インカ人やレオナルド・ダヴィンチが空を飛んでしまっていても都合が悪い。いまさら歴史の教科書を書きかえる訳にもいかない、「実はインカ人はナスカの地上絵を空から自分たちの飛行機で見ていました」と。
従って、オーパーツはたいがい、宇宙人もしくはムー大陸人の仕業かヤラセか捏造品ということで処理される。オーパーツというのは、「そもそも無かったんだよ、そんなもの」とか「見なかったことにしてさっさと忘れて、さあ平穏無事な日常に戻ろう」という代物だ。
私にとっても、初めて聴いたオープンリールデッキの音は、オーパーツであって欲しいと切に願っている。
大して考古学的な価値を見出されることもなく、歴史の教科書を塗り替えることなく、無難に忘れ去られるオーパーツ。
しかしそれは確かにそこに存在していたものなのだ・・・
にほんブログ村 エッセイ・随筆
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
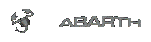
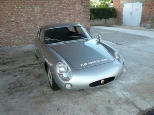
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
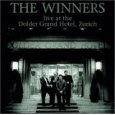
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
