×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
“久々にオーディオについてのネタでも”ということで、思い立ったように書こうと思ったのは電源関連についてだ。いい電源はいい音を生むという。オーディオに凝った人にしか分からない世界なのであろう。興味のない一般の方にとってはオカルティズムに近いことなのではないだろうか。
僕だってちょっと前には、手をかざすと病気が治るのと同じような印象だった。だが、雑誌では随分と沢山のページを割いているし、電気の波形を綺麗にしてやる装置だってあるのだ。世話になった建築設計事務所によると、前のめりにオーディオに邁進している層ばかりでなく、まあそれなりに<いい音>を聴きたいと考えている“マニアでない人”も、最近では電源に気を配るケースが増えて来ているという。割に電源対策が一般的になりつつあるのかもしれない。
とはいえ、本当にオーディオというのは本当に恐い世界だ。そのうちに小宅でも、とても小さな坪庭に植わる三本の竹の脇に、『MY電柱』を建立することになるやもしれない。家人による建設反対運動が起こるのは必至であるが。
それで我がオーディオ部屋の電源についてだが、元のブレーカーは中で家庭用とオーディオ用の二系統に分けている。ただし、ただ分けたというだけであって、オーディオ用は特別にフジクラの電線にして壁の中を渡しているという訳ではないし、ブレーカーそのものも一般家庭用のものだ。だから我が家の三階にある元のブレーカーからどのメーカーの電線でもって地下まで通しているのかも判然としない。でもまあ、まだ分けただけマシだとしよう。
このオーディオ用は二階のリビングと地下に分波されている。リビングには家人の強い要請で、いわゆる単なるミニコンポが設置されている。リビングには脇にキッチンがあるのであって、料理を作りながら凝ったオーディオのシステムなどを聴かされても困るということだ。<いい音>過ぎても困ると。何かをしながら音楽をBGM的に流すという目的もあるので、<気にならない音>である必要がある。オーディオにはこういう選択の仕方もある。
決して馬鹿にしているのではなく、何もどうしても<いい音>である必要はないのだ、オーディオというものは。そういうスタイルがあったっていい。こんなことは当たり前のことだ。ハイエンドこそ“正しいオーディオ”というのは幻想だ。
何に怒ったのかは自分でもよく分からないが、それはさておき、とはいえリビングの壁コンにはオヤイデの<SWO-XXX ULTIMO>を付けた。安いコンポーネントだからこそ、よいコンセントが利くだろうと考えたからだ。これは事実正解であった。オヤイデとその隣の普通の家庭用コンセントでは、ミニコンポをつないだ時の印象がまるで違う。家人もこれには驚いていた。がゆえに、壁コンは非常に投資効果の高い商品だといえる。
長くなったが、やっと地下だ。コンセントは全部で7個ある。家庭用が4個(うち1個は壁上部のエアコン用)、オーディオ用が4個。そのオーディオ用は二つが松下電工のホスピタルグレード<WN-1318>、電源対策の基本と言われるやつだ。色を何色にするか随分悩んで、茶色を選んだ。家を建てる時に自分で買って、取り付けるよう業者の人にお願いしたのだが、なかなかインテリアにあう色だと思ったのであろう。サービスで家庭用の3個のコンセントもこれと同じにしてくれた。これはラッキーであった(大して高くないですからね)。
他はレビトンのホスピタルグレード<8300>に、同じくレビトンの<クロームメッキの二口プレート>を2セット。『オーディオアクセサリー』誌をよく読んで、各社の傾向を字面で大体つかんだが、何にせよ、コンセントによって音に余計なカラーレーションが付帯するのは避けたいと考えていた(この流れと47研製品の導入はもちろん連動している)。だからオヤイデを地下に設置することは当初から計画していなかった。比較的ピュアな素性の壁コンを導入するつもりであった。僕の場合、例によって見た目も重要なファクターである。床の墨色に合わせるためにコンセントの色は黒として、壁面のコンクリート打ち放しの無機質な感じに適するカッコいいプレートを探すうちに、レビトン社製に辿り着いた。
家を建てている最中にコンセントを選ぶ作業をしたのだが、家は当然出来ていない訳で、まだ見ぬ部屋の雰囲気にあわせようと、来る日も来る日もイマジネーションを働かせて想像を繰り返した。設置されてしまえばなんのことはない、インテリアにとっては単なる脇役なのであるが、あーでもない、こーでないと選んだからこそ、<いい音>に聴こえるというものである。電気工事の資格もないので、他コンセントとの比較は適わないが、そう勝手に信じ込むようにしている。
PR
草思社と新風舎が民事再生法の適用を申請した。つまり分かりやすく言えば倒産ということか。
ともに以前、会社の仕事で関わりのあった先なので、特に草思社の方は驚きをもって受け止めた。ここの広告担当者は実によく自社の書籍を読んでいて、どの新聞にどの書籍の広告を出すのが効果的か、ということをかなり良く考えていた。その出稿理由を聞く度に舌を巻いたものである。
そもそも書籍のタイトルを決める際に、広告マーケティングの上席が会議に入って、編集サイドから挙がる候補に駄目を出し、こちらの題名の方が売れる、という”マーケティング”を意識した出版活動を行っていたので、僕はなおさら驚いた。
『声に出して読みたい日本語』、『間違いだらけのクルマ選び』。うまいネーミングだ。だから売れたのだろう。とりたてて経営がまずいというような風評も業界になかったように思うが、出版不況の煽りを受けて近日は売上が落ち込んでいたらしい。
書籍は多品種少量生産となって、なかなかベストセラーは出現せず、こと雑誌の中での数少ない勝ち組は、『CanCam』と一部の専門誌くらいなもので、出版不況はますます深まっているようだ。
インターネットが登場し、あっという間に浸透したお陰で、新聞も雑誌もテレビも、もはや多くの支持を集める媒体ではなくなりつつある。新聞の後退はここのところ顕著という向きが多い。テレビは広告収入が横ばいペースで推移しているようでもあるので、オールドメディアの中ではまだ何とか王者のポジションを堅持している。
さて、年末年始に煎餅をかじりながら、虫には逆にお尻をかじられつつ、テレビの視聴を熱心に進めた。テレビは何といっても、映像を以って分かりやすく番組制作をしているので、そんなに頭を使わずとも、内容がすんなり入って来る点が優れている。
年始のNHKで『イチロー』のインタビューを行っていた。いけすかない、クールな選手だ。取材への応対はとてもゾンザイに映ったが、海を渡ってもやはり常に首位打者争いをする男だ。唯一神が自分なのか野球なのかは分からないが、まるで修行僧のような生活を送っている(送っているように見えた)。
7年間、毎日昼飯はカレーだという。
体のコンディションをなるべく同じ状態で保つのが目的とはいえ、これは幾らなんでも凄い。私も10年ほど前に、同じく昼飯はカレーのみというのを先輩と冗談で1ヶ月の間実施したことがあるが、最後は拷問のように感じた。昼飯に限ったことではないが、どんなに好きでも7年というのは出来ない。これを見て思い出す場面が、そういえば同じ番組で過去にあった。某飲料メーカーのウイスキーブレンダーがその会社の食堂に行くと、黙っていても“掛けそば”が出て来るというシーンだ。ウイスキーの味を決める責任者である彼も、自分の体調を一定に保つために、舌が狂わないよう、昼飯の種類を長らく固定していた。
その道のプロ、第一人者ともなると、分野は違えど共通点が出て来るというのは興味深い。
また、何でもイチローの前シーズンは、異次元の挑戦を行っていたらしい。過去の栄光をかなぐり捨てて、真っ向から自らに降りかかる重圧に対峙したのだ。人間だれしも、今までの自分をあっさりと捨てることなど適わない。だが、イチローはさらなる高みへと登攀すべく、過去の自分にしがみつかなかったという。
これはつまりマイルス・デイビスではないか。昨年、NHKで菊地成孔氏が講師を務めた『私のこだわり人物伝』は、まさに、過去の作品世界を否定し続け、貪欲に前のめりに歩み続けたミュージシャンとしてマイルスを取り上げていた。
ウイスキーのマスターブレンダーと同じ生活習慣を持ち、ジャズの帝王と同じ矜持で野球に取り組む男、鈴木一朗。その坊主頭からだけでなく、まるで修行僧のようであった。鬼気迫る表情を何度も垣間見せた。この人の周りに対する態度は横柄であるが、こと自分の仕事、手掛ける世界への妥協なき姿勢は、揺るぐことなく一流であった。
一流といえば、TBSでミノモンタが司会を務めていた古代ローマ帝国の番組も見た。塩野七生氏も指摘する通り、ジュリアス・シーザー(ユリウス・カエサル)は類まれなリーダーだったという件で印象的なエピソードが紹介された。昼夜を問わずに行軍し、軍隊の指揮を執り続けたカエサルが、樹に寄りかかって眠ってしまうと、その傍らを通る兵隊は自分の甲冑が音をたてないよう気遣ったというのだ。戦地に赴かずに本国で兵站を分析するとか、たとえ戦地にいてもいつも最後方に控えて泥仕事をしないようなリーダーではなく、率先して行動で示す尊敬すべきリーダーであったのだろう。
そのミノモンタの番組の前の晩、これもNHKで『私のこだわり人物伝“スペシャル”』というのを放送していた。マイルスも取り上げたのだが、チェ・ゲバラに私はカエサルをダブらせた。奇跡のキューバ革命を実現させた後、工業相となったゲバラは、労働者と一緒になって、それこそ朝から晩まで力仕事に汗を流した。そうしなければ民衆が何を望んでいるのか、社会文化を発展させるために何が問題となるのか、が分からないと思っていたらしい。
今時、こんな宰相はいない。誰が好き好んでサトウキビを摘むというのか。
カエサルもゲバラも、理想の道半ばで挫した悲劇のヒーローであるから、後世によって多分に美化されるにしても、リーダーの条件や才覚というものは、古今東西を問わないものだと改めて感心した。いつの時代も指導者に求められることというのはさして変わらぬようだ。
と、ここまで来るとNHKの番組賛歌のようになってしまって、ちょっと居心地が悪いので、苦言を呈しておく。年末恒例の紅白歌合戦だ。全てを見通したというよりも、忙しく格闘番組とザッピングをしていたのだが、今年のNHKの紅白は、“ただ単にNHKが時代(の芸能)と寝た”としか映らなかった。
どういうことかといえば、今の時代を真っ向から全て是認したような、たとえ問題があったとしてもお祭り気分なのだから、あえてくどくど説明する必要はありませんよね、と開き直ったような印象を受けたのだ。
AKB48ほかの少女軍団を登板させることで、おじいちゃんおばあちゃん以外の若者層をアザトク惹きつけようとしたのであろうが、では健気に見えるこの多くの少女達を重用することで、彼女らを性の対象とする輩が爆発的に増大し、のっぴきならない犯罪を引き起こす遠因になっていることをどう説明するのか(もはや彼女らの学芸会の様子をテレビで垂れ流し続ける必要はないのではないか)。ただ単に我らが紅白に視聴(率)が戻りさえすればそれでよい、とはいえないはずだ、仮にも国営放送なのだから。
加えて、中村中が赤組(女性)として、美川憲一は白組(男性)として、槙原ノリユキは当然といえば当然なのかもしれないが白組に入っていた。性同一性症候群とは病気の名前のように聞こえるが、彼らは社会的弱者でまだまだ偏見や差別の対象だ。なぜ忌み嫌ったり避けたりするかといえば、そうでない人からすると“一体何だかよく分からない”からだ。なぜそのような病気(症候群)が発生するのか、日本にはどのくらい推定いるのか(一説には国内でも一千万人を超すとのことだが)、世界ではどうなのか。
なぜ同性愛者は増えつつあるのか(増えているように見えるのか、マヤにも江戸にも男色は多数いたのであるから)。タブー視されるのは、DNAに刻まれた子孫繁栄の志向を否定される恐怖ばかりでなく、厳然と存在するある嗜好や価値観の人達を、(そこにいるのに)見て見ぬ振りをしたい社会の要請があるからだろう。都合の悪いもの、説明のつきにくいものは、見えていても、見えない振りや何となくやり過ごすのが今の日本の雰囲気だ。
今回のNHKによる歌手の仕分けは、説明が足りない。“何となくそういうことだ”という社会的雰囲気でしか視聴者を納得させていない。このジェンダーに関わる重要な問題も、特にNHKが番組を通じて教示して欲しいテーマであるにも関わらず。
という具合で、手法は何でもいいから視聴者を舞い戻そうという形振り構わぬ切羽詰った感じと、“今の時代というのは何となくこういうことですよね”みたいな慇懃な慣れなれしさを感じさせた今年のNHK紅白だった。
さて、年末年始に煎餅をかじりながら、虫には逆にお尻をかじられつつ、テレビの視聴を熱心に進めた。テレビは何といっても、映像を以って分かりやすく番組制作をしているので、そんなに頭を使わずとも、内容がすんなり入って来る点が優れている。
年始のNHKで『イチロー』のインタビューを行っていた。いけすかない、クールな選手だ。取材への応対はとてもゾンザイに映ったが、海を渡ってもやはり常に首位打者争いをする男だ。唯一神が自分なのか野球なのかは分からないが、まるで修行僧のような生活を送っている(送っているように見えた)。
7年間、毎日昼飯はカレーだという。
体のコンディションをなるべく同じ状態で保つのが目的とはいえ、これは幾らなんでも凄い。私も10年ほど前に、同じく昼飯はカレーのみというのを先輩と冗談で1ヶ月の間実施したことがあるが、最後は拷問のように感じた。昼飯に限ったことではないが、どんなに好きでも7年というのは出来ない。これを見て思い出す場面が、そういえば同じ番組で過去にあった。某飲料メーカーのウイスキーブレンダーがその会社の食堂に行くと、黙っていても“掛けそば”が出て来るというシーンだ。ウイスキーの味を決める責任者である彼も、自分の体調を一定に保つために、舌が狂わないよう、昼飯の種類を長らく固定していた。
その道のプロ、第一人者ともなると、分野は違えど共通点が出て来るというのは興味深い。
また、何でもイチローの前シーズンは、異次元の挑戦を行っていたらしい。過去の栄光をかなぐり捨てて、真っ向から自らに降りかかる重圧に対峙したのだ。人間だれしも、今までの自分をあっさりと捨てることなど適わない。だが、イチローはさらなる高みへと登攀すべく、過去の自分にしがみつかなかったという。
これはつまりマイルス・デイビスではないか。昨年、NHKで菊地成孔氏が講師を務めた『私のこだわり人物伝』は、まさに、過去の作品世界を否定し続け、貪欲に前のめりに歩み続けたミュージシャンとしてマイルスを取り上げていた。
ウイスキーのマスターブレンダーと同じ生活習慣を持ち、ジャズの帝王と同じ矜持で野球に取り組む男、鈴木一朗。その坊主頭からだけでなく、まるで修行僧のようであった。鬼気迫る表情を何度も垣間見せた。この人の周りに対する態度は横柄であるが、こと自分の仕事、手掛ける世界への妥協なき姿勢は、揺るぐことなく一流であった。
一流といえば、TBSでミノモンタが司会を務めていた古代ローマ帝国の番組も見た。塩野七生氏も指摘する通り、ジュリアス・シーザー(ユリウス・カエサル)は類まれなリーダーだったという件で印象的なエピソードが紹介された。昼夜を問わずに行軍し、軍隊の指揮を執り続けたカエサルが、樹に寄りかかって眠ってしまうと、その傍らを通る兵隊は自分の甲冑が音をたてないよう気遣ったというのだ。戦地に赴かずに本国で兵站を分析するとか、たとえ戦地にいてもいつも最後方に控えて泥仕事をしないようなリーダーではなく、率先して行動で示す尊敬すべきリーダーであったのだろう。
そのミノモンタの番組の前の晩、これもNHKで『私のこだわり人物伝“スペシャル”』というのを放送していた。マイルスも取り上げたのだが、チェ・ゲバラに私はカエサルをダブらせた。奇跡のキューバ革命を実現させた後、工業相となったゲバラは、労働者と一緒になって、それこそ朝から晩まで力仕事に汗を流した。そうしなければ民衆が何を望んでいるのか、社会文化を発展させるために何が問題となるのか、が分からないと思っていたらしい。
今時、こんな宰相はいない。誰が好き好んでサトウキビを摘むというのか。
カエサルもゲバラも、理想の道半ばで挫した悲劇のヒーローであるから、後世によって多分に美化されるにしても、リーダーの条件や才覚というものは、古今東西を問わないものだと改めて感心した。いつの時代も指導者に求められることというのはさして変わらぬようだ。
と、ここまで来るとNHKの番組賛歌のようになってしまって、ちょっと居心地が悪いので、苦言を呈しておく。年末恒例の紅白歌合戦だ。全てを見通したというよりも、忙しく格闘番組とザッピングをしていたのだが、今年のNHKの紅白は、“ただ単にNHKが時代(の芸能)と寝た”としか映らなかった。
どういうことかといえば、今の時代を真っ向から全て是認したような、たとえ問題があったとしてもお祭り気分なのだから、あえてくどくど説明する必要はありませんよね、と開き直ったような印象を受けたのだ。
AKB48ほかの少女軍団を登板させることで、おじいちゃんおばあちゃん以外の若者層をアザトク惹きつけようとしたのであろうが、では健気に見えるこの多くの少女達を重用することで、彼女らを性の対象とする輩が爆発的に増大し、のっぴきならない犯罪を引き起こす遠因になっていることをどう説明するのか(もはや彼女らの学芸会の様子をテレビで垂れ流し続ける必要はないのではないか)。ただ単に我らが紅白に視聴(率)が戻りさえすればそれでよい、とはいえないはずだ、仮にも国営放送なのだから。
加えて、中村中が赤組(女性)として、美川憲一は白組(男性)として、槙原ノリユキは当然といえば当然なのかもしれないが白組に入っていた。性同一性症候群とは病気の名前のように聞こえるが、彼らは社会的弱者でまだまだ偏見や差別の対象だ。なぜ忌み嫌ったり避けたりするかといえば、そうでない人からすると“一体何だかよく分からない”からだ。なぜそのような病気(症候群)が発生するのか、日本にはどのくらい推定いるのか(一説には国内でも一千万人を超すとのことだが)、世界ではどうなのか。
なぜ同性愛者は増えつつあるのか(増えているように見えるのか、マヤにも江戸にも男色は多数いたのであるから)。タブー視されるのは、DNAに刻まれた子孫繁栄の志向を否定される恐怖ばかりでなく、厳然と存在するある嗜好や価値観の人達を、(そこにいるのに)見て見ぬ振りをしたい社会の要請があるからだろう。都合の悪いもの、説明のつきにくいものは、見えていても、見えない振りや何となくやり過ごすのが今の日本の雰囲気だ。
今回のNHKによる歌手の仕分けは、説明が足りない。“何となくそういうことだ”という社会的雰囲気でしか視聴者を納得させていない。このジェンダーに関わる重要な問題も、特にNHKが番組を通じて教示して欲しいテーマであるにも関わらず。
という具合で、手法は何でもいいから視聴者を舞い戻そうという形振り構わぬ切羽詰った感じと、“今の時代というのは何となくこういうことですよね”みたいな慇懃な慣れなれしさを感じさせた今年のNHK紅白だった。
昨日は小雨の降る中、某オーディオ雑誌の編集長をされているKさんと学芸大学にあるコニシス研究所を訪問した。その雑誌の前回号で、小西さんのインタビュー記事が掲載されたこともあって、お伺いする運びとなった。
まずは、地下のコニシススタジオでしばし歓談。
今のオーディオシーンは、団塊世代の方々が戻って来つつあって元気を取り戻している、特に雑誌は調子がいいとのことだ(羨ましい限りで、新聞はいま絶不調で風邪をこじらせた老体はもう治る見込みがない、という話が業界で再び蔓延しています)。誌面に対する読者のレスポンスも上々らしい。しかしメーカーや流通は、まだ市場縮小の流れに喘いでいる。つまりオーディオに対する“関心”は戻って来たが、製品の“消費”やマーケットの“広がり”までは至っていないということだ。
そんな話をしながら、そこら中に無造作に置かれているプロ用の業務用機器について話題が移った。スチューダーのたくさんのメーターがついた機械を見て、オールドマークレビンソンに似ていると申し上げると、何とその機械の中身、つまりアンプ部分はレビンソンが作っていたのだという。スイスは時計産業で培った精密技術がゆえに、例えばボリュームの削り出しなどのメカの精度は素晴らしく高い。しかし、アンプの回路はあまり得意でなかったようで、レビンソンが請け負っていたのだ。
従って、レビンソンはプロシューマ-、コンシューマー両方を手掛けていたということか。いやむしろ、小西さんによれば、傑作といわれる『LNP-2L』もそもそもは、レコーディングの場面で録音ダビングなどに使えるような業務用の設計になっており、民生向けの製品ではなかったという。それを民生として使い出したのは日本のオーディオファイルであったという訳だ。
目から鱗の話を聞かせてもらって、僕は今回の訪問で一番の目的を果たすよう、そぞろ動き始めた。スタジオに設置されたJBL4311の音を聴くことだ。もともとは録音スタジオで使われることを想定して作られたスピーカーなのだから。果たしてプロのレコーディングスタジオで4311はどんな音で鳴っているのか。これをどうしても確認したかった。自分の4311と何が違うか、どこが同じなのか。
何でも小西さんがスタジオ事業をスタートさせた25、26歳の頃に、新宿のオーディオユニオンで購入したという。右も左も分からない時分に、スタジオをやるならスタジオモニターが必要だ、ということで手に入れたらしい。今ではプロ向けの機材を扱う様々な専門業者とのパイプがあるので、まさかオーディオユニオンで機材を買うことはないとのことだが、そういう昔のスピーカーがいまだに現役で活躍しているというのは、とても微笑ましい。

コニシスのスタジオに設えられた4311は年季が入っていて、仕事のできる職人みたいな肌艶をしていた。そしてまた、出て来た音にはガッツがあって、ずんずんと音が前に出てJBLらしさ満載という感じで、我が家と同じ音の傾向で安心した。同じスピーカーだから当たり前と言うなかれ。もしかしたらスタジオの4311はクラシックもよく鳴らしてしまうのではないかと思っていたのだ。しかし、シベリウスを掛けたら、これは僕の4311と同じように上手くは鳴らなかったので、安心したのだ。つまりはロックやジャズに向いたスピーカーなのだ。いずれにしても、素人というのは何でも確認しないと心が落ち着かないから大変だ。
スピーカーは壁面に埋め込まれ、わずかに前傾していた。音を大きくすると、壁ごと鳴らす豪快さで、壁もフロントバッフル面と化す。「やっぱりスタジオモニターというものはこうでなくっちゃ」と思う。この様子を見て、小宅のコンクリートの壁をぶち抜く決意を固めたことは言うまでもない。

さて、夜飯を食いに行くことになった。小西さんは普段から明るい性格だが、アルコールが入ると更に明るく饒舌になる。僕も負けじと、“イイチコ”でどくどくと燃料を注入した。席が終わる頃にはだいぶん酔っ払っていた。一回り上の先輩諸兄に失礼がなかったか気になるところではあるが、まああったとしても仕方あるまい。特に、理知的で紳士な印象のK編集長に呆れられてやしないか、非常に危惧するところなのであるが、しかしそういったことが心配なら酒は飲まない方がいい。いつまでもそんなことは言っていられないが、酒は呑まれてナンボである。
今日は頭が痛い、二日酔いのようだ。

まずは、地下のコニシススタジオでしばし歓談。
今のオーディオシーンは、団塊世代の方々が戻って来つつあって元気を取り戻している、特に雑誌は調子がいいとのことだ(羨ましい限りで、新聞はいま絶不調で風邪をこじらせた老体はもう治る見込みがない、という話が業界で再び蔓延しています)。誌面に対する読者のレスポンスも上々らしい。しかしメーカーや流通は、まだ市場縮小の流れに喘いでいる。つまりオーディオに対する“関心”は戻って来たが、製品の“消費”やマーケットの“広がり”までは至っていないということだ。
そんな話をしながら、そこら中に無造作に置かれているプロ用の業務用機器について話題が移った。スチューダーのたくさんのメーターがついた機械を見て、オールドマークレビンソンに似ていると申し上げると、何とその機械の中身、つまりアンプ部分はレビンソンが作っていたのだという。スイスは時計産業で培った精密技術がゆえに、例えばボリュームの削り出しなどのメカの精度は素晴らしく高い。しかし、アンプの回路はあまり得意でなかったようで、レビンソンが請け負っていたのだ。
従って、レビンソンはプロシューマ-、コンシューマー両方を手掛けていたということか。いやむしろ、小西さんによれば、傑作といわれる『LNP-2L』もそもそもは、レコーディングの場面で録音ダビングなどに使えるような業務用の設計になっており、民生向けの製品ではなかったという。それを民生として使い出したのは日本のオーディオファイルであったという訳だ。
目から鱗の話を聞かせてもらって、僕は今回の訪問で一番の目的を果たすよう、そぞろ動き始めた。スタジオに設置されたJBL4311の音を聴くことだ。もともとは録音スタジオで使われることを想定して作られたスピーカーなのだから。果たしてプロのレコーディングスタジオで4311はどんな音で鳴っているのか。これをどうしても確認したかった。自分の4311と何が違うか、どこが同じなのか。
何でも小西さんがスタジオ事業をスタートさせた25、26歳の頃に、新宿のオーディオユニオンで購入したという。右も左も分からない時分に、スタジオをやるならスタジオモニターが必要だ、ということで手に入れたらしい。今ではプロ向けの機材を扱う様々な専門業者とのパイプがあるので、まさかオーディオユニオンで機材を買うことはないとのことだが、そういう昔のスピーカーがいまだに現役で活躍しているというのは、とても微笑ましい。
コニシスのスタジオに設えられた4311は年季が入っていて、仕事のできる職人みたいな肌艶をしていた。そしてまた、出て来た音にはガッツがあって、ずんずんと音が前に出てJBLらしさ満載という感じで、我が家と同じ音の傾向で安心した。同じスピーカーだから当たり前と言うなかれ。もしかしたらスタジオの4311はクラシックもよく鳴らしてしまうのではないかと思っていたのだ。しかし、シベリウスを掛けたら、これは僕の4311と同じように上手くは鳴らなかったので、安心したのだ。つまりはロックやジャズに向いたスピーカーなのだ。いずれにしても、素人というのは何でも確認しないと心が落ち着かないから大変だ。
スピーカーは壁面に埋め込まれ、わずかに前傾していた。音を大きくすると、壁ごと鳴らす豪快さで、壁もフロントバッフル面と化す。「やっぱりスタジオモニターというものはこうでなくっちゃ」と思う。この様子を見て、小宅のコンクリートの壁をぶち抜く決意を固めたことは言うまでもない。
さて、夜飯を食いに行くことになった。小西さんは普段から明るい性格だが、アルコールが入ると更に明るく饒舌になる。僕も負けじと、“イイチコ”でどくどくと燃料を注入した。席が終わる頃にはだいぶん酔っ払っていた。一回り上の先輩諸兄に失礼がなかったか気になるところではあるが、まああったとしても仕方あるまい。特に、理知的で紳士な印象のK編集長に呆れられてやしないか、非常に危惧するところなのであるが、しかしそういったことが心配なら酒は飲まない方がいい。いつまでもそんなことは言っていられないが、酒は呑まれてナンボである。
今日は頭が痛い、二日酔いのようだ。
カテゴリー
■メールでのお問い合わせ、
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
ご連絡は、本Webページの最下部に設置しております
メールフォームからお願い
します。
-------------------------------
プロフィール
HN:
なし
性別:
男性
自己紹介:
powerd by
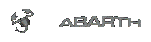
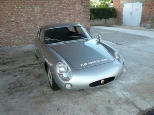
powerd by
最新コメント
[08/15 yrndmifoaj]
[08/15 ekckyuobwa]
[08/14 clqoizbepn]
[07/19 azart47]
最新トラックバック
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター
フリーエリア
建築家の設計による狭小住宅からブログ発信中。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
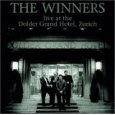
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
地下の書斎でオーディオを
愉しみ、音楽はなかでも特にJAZZ(ジャズ)を聴きます。
《お知らせ》直近の雑誌寄稿
→左記、カテゴリー《メディアへの寄稿》からご覧下さい
-------------------------------
///聴かずに死ねない!JAZZライブ盤。現代JAZZの、ある到達地点に違いないです///
●詳細はこちらから(amazon)
The Winners/Live at the Dolder Grand Hotel, Zurich/TCB/2001
-------------------------------
M's Bar/男の書斎には、クルマやテニスなどの話題が中心のもう一つの別室ブログを設けています。
アーカイブ
リンク
